こんにちは!ITキャリアのプロです!

プロジェクトマネージャー(PM)の仕事は、単に進捗を管理するだけではありません。UX、組織構築、データに基づく意思決定など、横断的なスキルと知識が必要とされる高度な職種です。
「現場で試行錯誤しているけど、体系的な知識が欲しい」
「チームをうまくまとめられない…」
「ユーザー視点やデータ分析が弱いかも」
こう感じたことがある方にこそ、本記事で紹介する書籍は役立ちます。今回は、実務家・現役PMたちが推薦する良書16冊を、以下の4つのテーマで厳選して紹介します。
Contents
組織づくり・チームマネジメントが学べる本【リーダー必読】
1. エンジニアリング組織論への招待

キーワード:心理的安全性/不確実性のマネジメント
プロジェクトがうまく進まないのは、スキル不足や努力不足のせいではなく「不確実性」とどう向き合うかという“やり方”の問題かもしれません。
―組織に混乱が生まれるのはなぜか?
―若手が育たず、チームが伸び悩むのはなぜか?
―経営と現場がかみ合わないのはなぜか?
その答えはすべて、「不確実性」の中にあります。
本書は、数多くの技術組織アドバイザーとして活躍してきた著者がエンジニアリングにおける複雑な課題を構造的に捉え、“見える化”し、解きほぐしていくための考え方と具体的なアクションを提示してくれます。
PM・PdMにとっての注目ポイント
- チーム内外の認識のズレをどうなくすか
- 技術的負債をどう捉え、どう解消していくか
- 若手をどう育て、チーム全体を機能させるか
これらを支えるのは、「対話」と「構造化」、そして「文化の設計」という3つの観点です。言語化しにくいモヤモヤをクリアにし、成長し続ける組織をつくるための実践知が詰まっています。
「チームがうまくいかない理由がわからない」
「マネジメントに自信が持てない」
そんなPM・EM・リーダー層にとっての“必携の羅針盤”となる1冊です。デルや組織設計のヒントが詰まった、まさにすべてのプロジェクトマネージャー必携の書です。
2. Measure What Matters
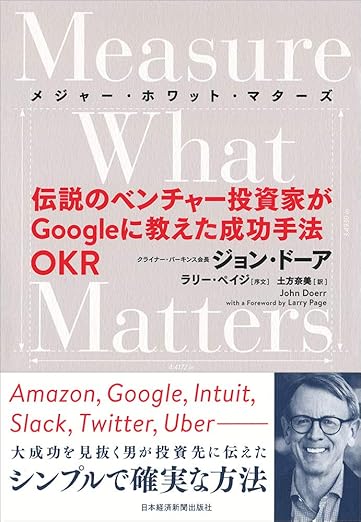
キーワード:OKR/目標設定/組織の一体化
「目標はある。でも、なぜか進まない」「チームがバラバラでまとまりがない」
そんなPMの“あるある”な悩みを根本から解決するのが、本書で紹介されているOKR(Objectives and Key Results)というシンプルで強力な目標管理フレームワークです。
本書の著者は、GoogleやAmazon、Twitterなどに初期投資したシリコンバレーの伝説的投資家ジョン・ドーア。彼が「GoogleにOKRを導入した立役者」として、OKRの原理と導入事例を多数紹介しています。
PM・PdMにとっての注目ポイント
- やるべきことを明確にし、チーム全体を一つの方向へ向ける方法
- 成果に直結しない“なんとなくの仕事”を削ぎ落とす判断力
- メンバーのエンゲージメントと責任感を高めるマネジメント手法
- チームの連携・アラインメントを高める仕組み
- 成果を“ストレッチ”させる挑戦目標の設計
Google、Slack、Intuitなどの企業事例が満載で、「OKRって理想論でしょ?」と思っている人にこそ読んでほしい一冊です。プロジェクトの方向性を見失いがちな現場、目標が“空気”になってしまっているチームにとっては、まさに処方箋です。
PMとして、単なる管理者から「成果を出す組織の仕掛け人」になりたいなら、この一冊は間違いなくあなたの武器になります。
3. EMPOWERED 普通のチームが並外れた製品を生み出すプロダクトリーダーシップ
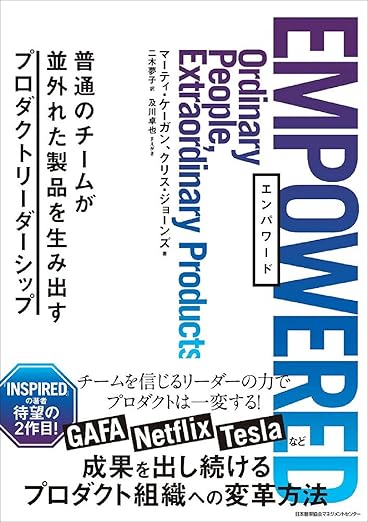
キーワード:プロダクト組織/自律性のあるチーム
本書では、著者マーティ・ケーガンが数十年にわたってトップテクノロジー企業の中で学んだプロダクトリーダーに求められる「育成」「組織づくり」「戦略設計」「ビジョン」といった多面的な力を実践的かつ体系的にガイドします。
PM・PdMにとっての注目ポイント
- チームを「指示待ち型」から「自律的な問題解決型」へ変える方法
- 優れた製品ビジョンの描き方とチームへの共有の仕方
- 人事・コーチング・コラボレーションまで含めた“全方位的なプロダクトリーダーシップ”
- 組織構造(チーム・トポロジー)と戦略をつなぐ設計力
- ケーススタディを通じた、現場での実践法
単なるプロダクトマネジメント本ではなく「強いチームをどう育てるか」にフォーカスした、すべてのPM/EMの成長の道しるべ。
チームの力を信じて任せたいけれど、どうすればうまく導けるかわからない――そんな悩みを抱えるすべてのリーダーに贈る、“自律駆動型組織”への変革書です。
4. チームトポロジー 価値あるソフトウェアをすばやく届ける適応型組織設計
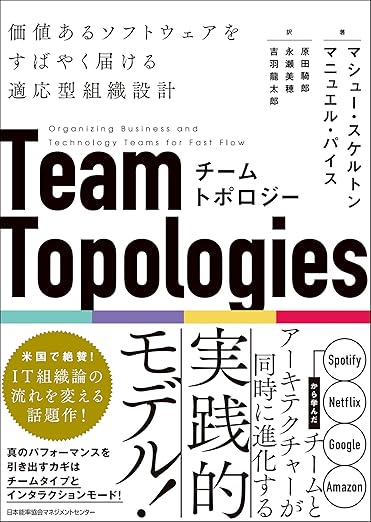
キーワード:チーム構造設計/DevOps/スケーラビリティ
本書では、アジャイル・DevOps時代のチーム運営において不可欠となる、以下のようなフレームワークを紹介しています。
- 4つの基本的なチームタイプ(ストリームアラインド/コンプリケイテッドサブシステム/プラットフォーム/イネイブリング)
- 3つのインタラクションモード(協調/X-as-a-Service/ファシリテーション)
- チーム構造を自己進化させる「組織的センシング」
PMが押さえておきたい注目ポイント:
- コンウェイの法則を活かした「アーキテクチャと組織構造の整合」
- チームの境界を明確にすることで、責任と自律性を両立させる手法
- サイロ化・依存の泥沼から脱却するインタラクション設計
- 組織の“適応力”を高める、構造化されたチーム進化のプロセス
プロジェクトを「どう進めるか」だけでなく、誰が・どこで・どう連携するかを意識して設計することは、今やPMの必須スキルです。
『チームトポロジー』は、こうした組織設計の観点からプロジェクト成功を支える“チームビルディングの再定義書”。マネージャー・PdM・テックリードすべての立場で、「今、自分たちの組織はこの形でいいのか?」と問い直すきっかけをくれる一冊です。
UX・ユーザー視点のプロジェクトを学べる本【デザイナーPMにも】
5. はじめてのUXリサーチ ユーザーとともに価値あるサービスを作り続けるために
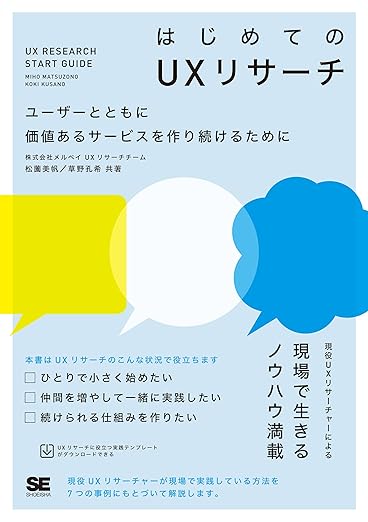
キーワード:ユーザー理解/インタビュー設計/共感のデザイン
本書は、現場経験豊富なメルペイのUXリサーチャーたちが執筆した、UXリサーチの本質から現場への落とし込みまでを丁寧に解説する入門書。UXリサーチの「考え方・設計・実践・共有」までを、以下のような観点で学べます。
PMが押さえておきたい注目ポイント
- ユーザー理解を“チームで共有できる”状態にするための調査設計
- ひとりでも小さく始められるリサーチの始め方・仲間の巻き込み方
- 意思決定を「エビデンスドリブン」に変えるための実践テンプレート
- メルペイで実際に行われている7つのリサーチ事例を通じた現場ノウハウ
- 継続的なUX活動をチームに定着させる仕組みづくり
プロジェクトを進めるうえで、「何が正しいのか」に自信が持てないとき、
PMが頼るべきは“声の大きい人の意見”ではなく、“実際のユーザーの声”です。
UXリサーチはその橋渡しとなる、現代プロダクト開発における不可欠なスキルセット。
本書は、リサーチ未経験のPMでもすぐに実践できるヒントと仕組みを提供してくれる、まさに“最初の一歩”にぴったりの一冊です。
6. UXリサーチの道具箱
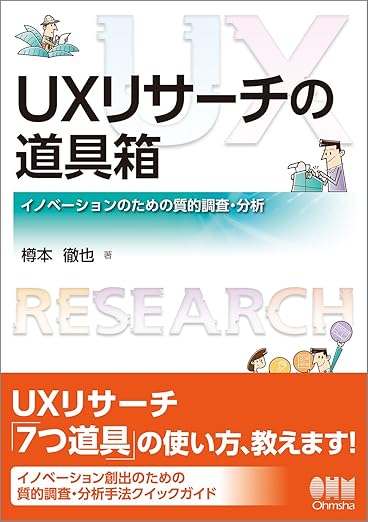
キーワード:調査技法/実践ノウハウ/多角的アプローチ
UXリサーチとは、アンケートや購入意向のような「表層データ」を集めることではありません。
ユーザーの行動や価値観に深く入り込み、“私たちの思考や前提を揺さぶる洞察”を引き出す技術です。
本書では、人類学に由来するアプローチをベースにした「UXリサーチ7つ道具」を紹介しています。各章は独立しており、どこからでも読める構成になっています。
PMが押さえておきたい注目ポイント:
- ユーザインタビューやペルソナ、カスタマージャーニーなど、実務に直結する基本ツールを体系化
- 「ジョブ理論」や「キャンバス」など戦略設計に活かせる思考モデルもカバー
- 1章1万字前後でサクッと読めて、実務にすぐ活かせる構成
- イラスト豊富でチーム内共有にも最適。視覚で理解しやすい
- 各章末の読書ガイドで知識をさらに深掘りできる
UXリサーチは、もはや“専門職だけの仕事”ではありません。PMこそがユーザー理解のハブとなり、チーム全体を正しい方向に導く立場にあります。
この一冊は、PM・デザイナー・エンジニア・起業家など、あらゆる「顧客価値」を扱う人にとってのリサーチの道しるべとなるはずです。ユーザーの「本音」と「本質」を見抜く目を養いたいすべての人におすすめします。
7. ユーザーストーリーマッピング
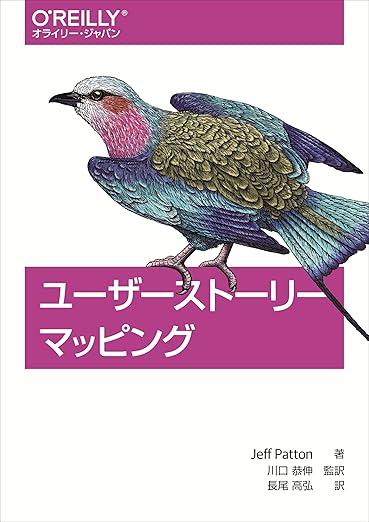
キーワード:ユーザーストーリー/アジャイル開発/共通認識
本書では、ストーリーマッピングの全体像を、以下のような流れで体系的に解説しています:
- ストーリーマップの基本構造と作成のステップ
- ストーリーを“仕様”ではなく“対話のきっかけ”として活用する思考法
- マッピングを通じてプロダクトビジョンをチームで共有する技術
- ドキュメントと会話を両立させるアジャイル実践の要点
PMが押さえておきたい注目ポイント:
- User Story Mappingは一人で作るものではない
⇒ 会話を通じてこそ、真の価値と共通理解が生まれる - マップは“設計図”ではなく“対話のたたき台”
⇒ チームがユーザー目線で議論できる土台をつくる - アジャイルだからこそ、ドキュメントが重要
⇒ 必要な情報は“話して記録”。リアルタイムで残すのが肝 - プロダクト作りは“世界を変える仕事”である
⇒ ただの作業ではなく、ユーザーの1日をよりよくする発想を持つ
実際にこの本に救われた現場の声もあります。「一人で黙々と作っていたバックログが、チームで“語り合いながらつくるもの”に変わった」と語るPMの体験談は、多くの現場に共通する課題を示唆しています。
ユーザーストーリーマッピングは、仕様書では伝えきれないニュアンスを、会話と構造化でチームに届ける技術。「どうすればズレなく、速く、価値ある開発ができるか」を模索するすべてのPMにとって、間違いなく武器になる一冊です。
8. マッピングエクスペリエンス ―カスタマージャーニー、サービスブループリント、その他ダイアグラムから価値を創る
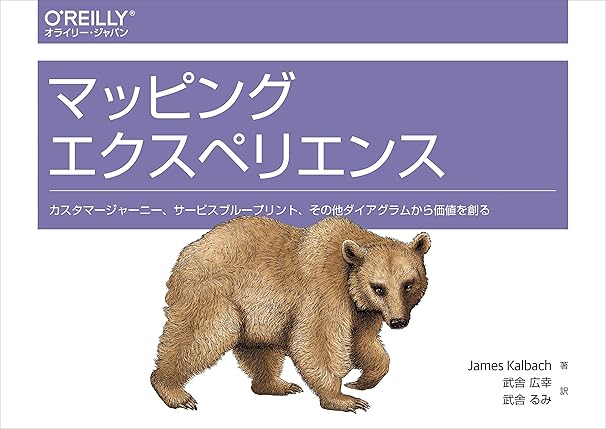
キーワード:ジャーニーマップ/サービス設計/視覚思考
本書は、カスタマージャーニーやサービスブループリントをはじめとする各種マップを、以下の4段階で活用するフレームワークを紹介しています:
- ステージ1:プロジェクトの目的・視点を定義する「開始」
- ステージ2:顧客理解を深める「調査」
- ステージ3:気づきを構造化する「作成」
- ステージ4:チームを巻き込む「連携」
PMが押さえておきたい注目ポイント:
- UXとビジネスを“タッチポイント”でつなぐ、全体設計のスキルが身につく
- サービス設計において部門横断で議論できる「共通言語」が手に入る
- メンタルモデル、エクスペリエンスマップなど、用途別の図解手法を習得できる
- 形式よりも“意味の伝達”を重視するマッピング思考が学べる
- UXの文化を組織内に根付かせるための「ビジネスマインドセット」も豊富に掲載
プロジェクトマネージャーにとって、図を描くことは目的ではなく、共通認識を作り出し、連携を生むための手段です。とくに大規模プロジェクトや複数部署が関わる製品開発において、「ユーザーは今、何を感じているか」を全員が見られる状態にすることが、成功への鍵となります。
本書は、UXの専門家だけでなく、ビジネスサイドや開発チームを巻き込みながら“体験設計”をリードしたいPMにとっての最強のガイド。見えない“ユーザーのこころの動き”をチームの意思決定に反映させたい人に、必ず刺さる一冊です。
データを活かすプロジェクトマネジメント本【意思決定の武器】
9. DMM.comを支えるデータ駆動戦略
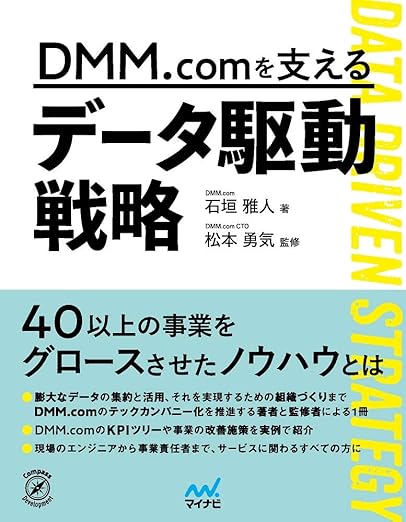
キーワード:データドリブン/組織改革/事業成長
本書は3つのパートで構成されており、PMにとっても特に重要な知見が詰まっています:
- Part1:データ駆動戦略の全体像
事業を“感覚”で捉えるのではなく、数値モデルやKPIで構造的に理解するフレームワーク - Part2:体制づくりと仮説検証のプロセス
アジャイルとデータ分析を掛け合わせ、「短期で確実に学ぶ」ための開発とチーム設計 - Part3:データ民主化とプロダクト横断の学習基盤
誰でもデータを活用できる文化・技術基盤をどう構築しているかを紹介
PMが押さえておきたい注目ポイント:
- 「感覚」ではなく「観測」による意思決定を実現するフローと仕組み
- データが分散していてもまずは集約 → 整理 → 活用の流れ(データレイク→DWH→マート)
- 属人的な判断ではなく、再現性のある“学習可能な組織”を育てる考え方
- 失敗の記録こそがナレッジ。改善の確率を高めるために失敗を恐れない文化
- A/Bテストの前にA/Aテストを実施するなど、データ分析の前提力も実用的に解説
プロジェクトを“なんとなく”で進めるのではなく、判断の背景を明確にし、失敗すらも資産に変えていく仕組みが今、PMに求められています。
本書は、データ活用が未成熟な組織に対して「まず何から始めるべきか」「どう組織文化に定着させるか」をリアルに教えてくれる一冊。プロダクトを育てるだけでなく、チームを“学習し続ける集団”へ導きたいPMにとって、まさに必携の戦略書です。
10. ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム
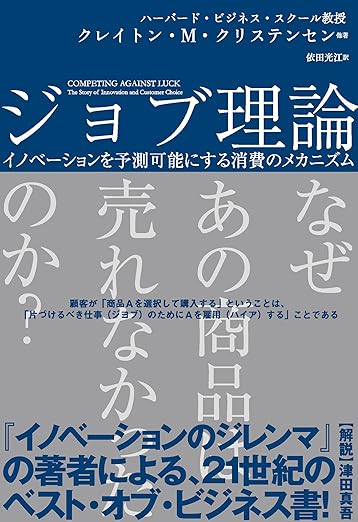
キーワード:顧客インサイト/イノベーション/ニーズ分析
本書では、ユーザーの“購入行動”の背後にある因果関係を見抜くための思考法と、
それをプロダクト戦略に落とし込むためのアプローチを、豊富な事例とともに解説しています。
PM・PdMが押さえておきたい注目ポイント:
- 顧客を「属性」で切るのではなく、「やりたいこと(ジョブ)」で理解する
- ビッグデータでは見えない“本当の購買理由”を洞察する力を養える
- “競合は同業ではなく、代替手段や無消費”という視点の転換
- 機能だけでなく、感情的・社会的なニーズを含めたプロダクトの再設計
- 組織全体を“ジョブ中心”に再構成するマネジメント論もカバー
イノベーションを“ひらめき”や“センス”に頼るのではなく、「なぜそれが選ばれるのか」を構造的に説明・再現できる方法論としてジョブ理論は非常に強力です。
とくにプロジェクト初期の要件定義や、PMF(プロダクトマーケットフィット)を目指す段階において、「自分たちの製品は、ユーザーのどんな1日を変えるのか?」という視点を持つことで、プロダクトの方向性がブレなくなります。
単なる理論にとどまらず、UX・マーケ・組織設計・教育・医療など、さまざまな領域で応用が利くのも魅力。
プロダクトマネージャー・起業家・ビジネスサイドのリーダーにとって、“モノではなく価値を届ける”思考を育てる必読書です。
11. ラディカル・プロダクト・シンキング イノベーティブなソフトウェア・サービスを生み出す5つのステップ
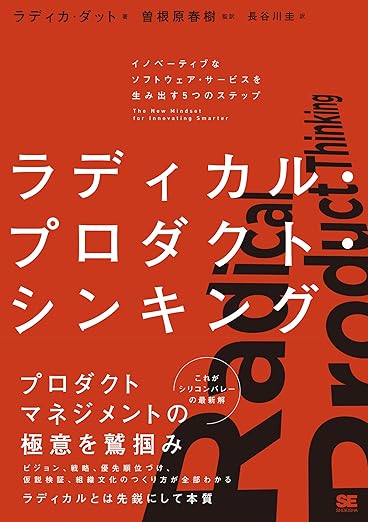
キーワード:ミッションドリブン/戦略設計/アクションプラン
著者が提示する「プロダクトを成功に導く5つのステップ」は、以下の通り。
- 組織と市場にマッチしたビジョンのつくり方
- ビジョンを達成するための戦略の立て方
- 戦略に基づいた優先順位づけ
- 仮説をもとにした実行と検証
- 組織文化へビジョンを浸透させる方法
PM・PdMが押さえておきたい注目ポイント:
- プロダクトを“成果”ではなく“変化”として定義する、価値起点の思考法
- ミッションドリブンな意思決定と、短期成果を両立させる優先順位の設計術
- 仮説検証の繰り返しに振り回されず、本来の目的に立ち返るフレームワーク
- 組織文化や行動の深層に働きかける、長期視点のプロダクトリーダーシップ
- 社会・倫理・未来への視座をもった、スケールするビジョン設計論
PMとして迷子になったとき、“この機能で誰の人生がどう変わるのか”を問う勇気と方向性を取り戻させてくれるのがこの本です。本書は、単なる「戦術書」ではありません。それは、プロダクトを通じて人や社会にどう貢献するのかを再定義し、プロジェクトを“意味ある仕事”に変えていく思想とツールの指南書です。
日々の優先順位に埋もれそうになったPMにこそ届けたい、“原点に立ち返る一冊”です。
12. 起業の科学 スタートアップサイエンス
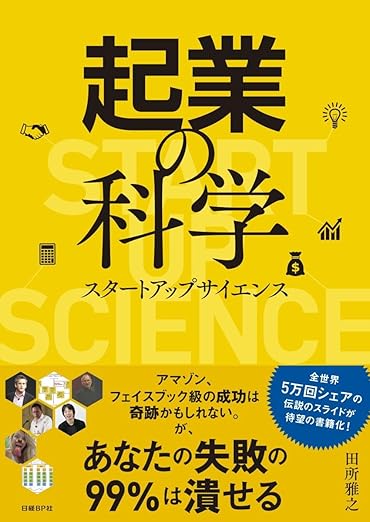
キーワード:MVP/リーン思考/PMF
本書では、起業初期からPMF(プロダクト・マーケット・フィット)、そしてスケールフェーズに至るまで、以下のようなプロセスを段階的に学べます。
- アイデア検証(IDEA VERIFICATION)
- 課題検証(CUSTOMER PROBLEM FIT)
- 解決策検証(PROBLEM SOLUTION FIT)
- 市場適合(PRODUCT MARKET FIT)
- スケール(TRANSITION TO SCALE)
PM・PdMが押さえておきたい注目ポイント:
- アイデアを“思いつき”ではなく“検証対象”として扱う、科学的な起業思考
- 市場に聞く前に、ユーザーの「課題の質」を徹底的に高めるアプローチ
- 「良いアイデア=成功」ではない現実と、進むべき順序の理解
- スケールのタイミングで陥る組織の病と、対処のフレームワーク
- スタートアップだけでなく、新規事業や副業にも応用できる実践知
この本は、ただの起業本ではありません。それは、「アート(感覚)」になりがちなスタートアップを、“科学”という再現可能な方法論で成功に近づけるマニュアルです。プロダクトを“当てる”のではなく、“育てて届ける”ために。PMやプロダクトリーダーとして新規事業に関わる方、ゼロイチに挑む全ての人にとって、絶対に読んでおくべき一本です。
13. リーン・スタートアップ
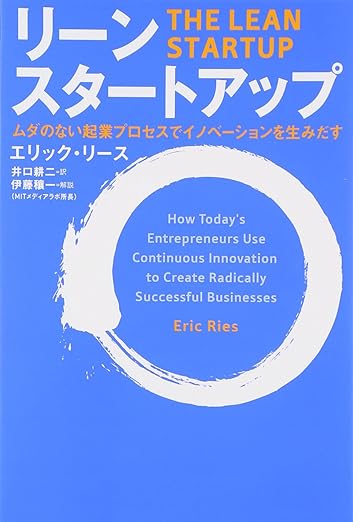
キーワード:仮説検証/反復開発/スタートアップ手法
本書が提唱するのは、ただの「早く作る」ではありません。
「構築 → 計測 → 学習」という科学的サイクルを回すことで、プロダクトの価値を早期に見極め、最小限の失敗で最大限の成長を狙うという、再現性あるアプローチです。
PM・PdMが押さえておきたい注目ポイント:
- MVP(Minimum Viable Product)で顧客反応を素早く検証する設計力
- ピボット or 辛抱の意思決定を、定量的に見極めるフレームワーク
- 価値仮説・成長仮説の立て方と、それに基づく学びのサイクル
- イノベーションを“数字で管理”する「革新会計(イノベーションアカウンティング)」の導入方法
- 検証を“日常業務”に組み込むことで、チームが継続的に改善できる仕組み
本書が教えてくれるのは、スピードやアジリティだけではありません。
それは、「価値ある学び」に到達するまでの最短経路をどう設計するか」という問いに対する、具体的な実践知です。特に、プロジェクト初期で「完璧な計画」を求めすぎて前に進めなくなっている人にとって、
「動いてから学ぶ」ことの重要性と安心感を与えてくれる一冊です。
スタートアップだけでなく、大企業の新規事業・副業開発・サービス改善にも応用可能。プロダクト開発を“試行錯誤から、意図ある検証”へと進化させたいすべてのPMにおすすめの必読書です。
プロダクトマネジメントを体系的に学べる本【すべてのPMの基礎力】
14. INSPIRED 熱狂させる製品を生み出すプロダクトマネジメント
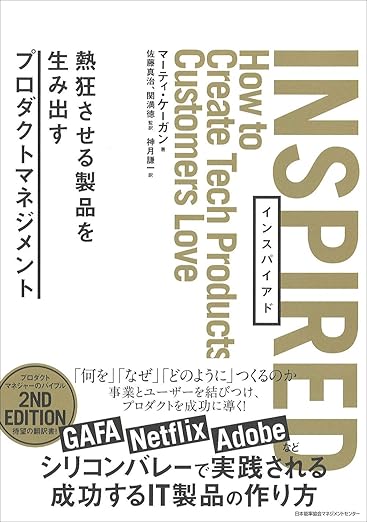
キーワード:プロダクトマネジメント全体/顧客中心/チームの動かし方
本書では、単に「作る・管理する」だけではない、ユーザーに愛される製品をどう発見し、どう組織で実現するかにフォーカスしています。特に印象的なのは、プロダクトマネージャーが持つべき責任の定義。
それは「正しい製品を見つけること」であり、そのために必要なチーム構成・思考法・検証プロセス・文化の作り方が余すところなく語られます。
PMが押さえておきたい注目ポイント:
- 顧客に本当に必要とされる「製品の発見(Product Discovery)」を担うのがPMの本質
- ロードマップに縛られず、仮説ベースで高速に学習する“強いチーム”のつくり方
- デザイナー・エンジニアと三位一体で価値を届ける「トリオ型チーム」の考え方
- 製品アイデアを検証・改善していくプロトタイプやユーザーテストの実践ノウハウ
- 成長段階に応じたチーム構造とスケール戦略、プロダクト文化の育て方
欧米企業中心の事例ではあるものの、NetflixやGoogle、Appleなどの具体例がふんだんに紹介されており、
「PMとは何者か?」「どう価値を生み出すのか?」を根本から学びたい方にはうってつけの一冊です。
プロダクトを“管理”するのではなく、“発見し、形にし、届ける”。ユーザーに本当に必要とされる製品を生み出したいすべてのPMにとって、読まない理由が見つからない一冊です。
15. プロダクトマネジメント ―ビルドトラップを避け顧客に価値を届ける

キーワード:ビルドトラップ/成果思考/価値創出
著者メリッサ・ペリは、プロダクトマネジメントを次の3つの観点で体系化しています。
- 戦略と意思決定:PMは「なぜこれを作るのか?」を明確にできなければならない
- 仮説と検証:顧客の課題を検証し、実験と最適化によって価値ある解決策を見出す
- 組織と文化:プロダクト思考を根づかせ、全社で「顧客中心」に取り組む仕組みをつくる
PMが押さえておきたい注目ポイント:
- プロダクトマネージャーの役割は「プロダクトの社長」ではない
─ CEOの真似をするのではなく、人間性と説得力で周囲を巻き込むリーダーシップ - プロジェクトマネジメントとの違い
─ PMは「なぜ作るのか」に責任を持ち、組織に“納得感”を与える存在 - プロダクト主導の組織設計
─ アウトカムを中心に据えた評価指標・KPI・文化づくりの実践知が豊富 - トヨタの主査制度との接点
─ 製品の成功を一手に背負い、技術・ビジネス・デザインを横断する“調整と統合”の役割がPMにも求められる
本書は欧米で語られがちな「PMはミニCEOである」という誤解を正し、プロダクト開発における“共感と納得を育てるリーダーシップ”を実直に描いた一冊です。
ただ作るだけの組織から、成果を出す組織へ。
PMとして本当の意味で価値を届けたい人にとって、まさに“視座を引き上げてくれる教科書”になるでしょう。
16. プロダクトマネジメントのすべて 事業戦略・IT開発・UXデザイン・マーケティングからチーム・組織運営まで
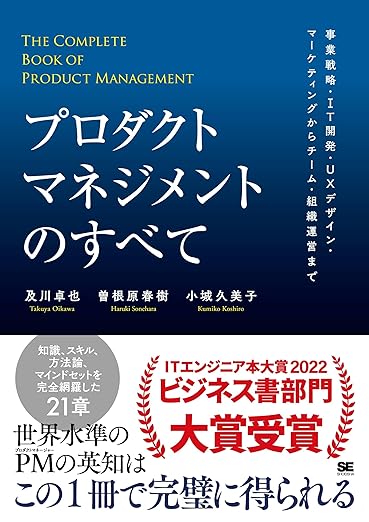
キーワード:国内実務/キャリア/開発・営業との連携
本書は「プロダクトを成功に導く全プロセス」を、6つのパートで網羅的にカバーしています。
- 戦略立案とビジョン設計:なぜ作るのか?誰のために?その本質を見つめ直す
- プロダクトの成長と改善:アイデアからPMF、継続的な仮説検証と学習へ
- チームとステークホルダーのまとめ方:心理的安全性・信頼・合意形成の築き方
- ビジネス環境理解:法務、知財、CS、セキュリティ、実務的観点まで
- 組織づくりとリーダーシップ:PM自身の成長と組織のスケール
- 基礎知識と用語:初心者にも親切な巻末のリファレンス
PM・PdMが押さえておきたい注目ポイント:
- ミッション・ビジョンとビジネスモデルを一貫性のある形で結びつける設計力
- チームの熱量と方向性を一致させる、キックオフ・ふりかえり・議事運営のノウハウ
- アウトプットではなくアウトカム(成果)で語る“プロダクト思考”の徹底
- 大規模開発とスピード重視の現場、それぞれの違いと共通する視点のバランス
- リモートワーク・アウトソース時代における「情報の見える化」の工夫
プロダクトづくりは、「作って終わり」ではありません。むしろ、リリース後からが本当のスタートであり、プロダクトとは“チームで学び続ける装置”でもあります。本書は、そんな現場のリアルに寄り添い、PM・エンジニア・UX・マーケ・CSといった全ての職種が、「自分たちの仕事が、どう価値につながっているのか」を明確に実感できる構成になっています。
「プロダクトマネジメントの全体像を掴みたい」「体系的に学びたい」と思ったときに、真っ先に手に取ってほしい“マスターピース”です。
まとめ|本でプロジェクトの成功率を最大化しよう
プロジェクトマネジメントの世界は、日々進化しています。
今回紹介した16冊は、それぞれ違う角度から「成功するプロジェクト」の本質に迫る本ばかりです。
- ✅ チームを強くしたいなら→ 組織・チーム系
- ✅ 顧客をもっと理解したいなら→ UX・デザイン系
- ✅ データで判断したいなら→ 分析・戦略系
- ✅ すべてのPMの基礎力を身につけたいなら→ プロダクトマネジメントを体系的に学べる系
あなたの今の課題にマッチする1冊を手に取り、ぜひ現場に活かしてください!

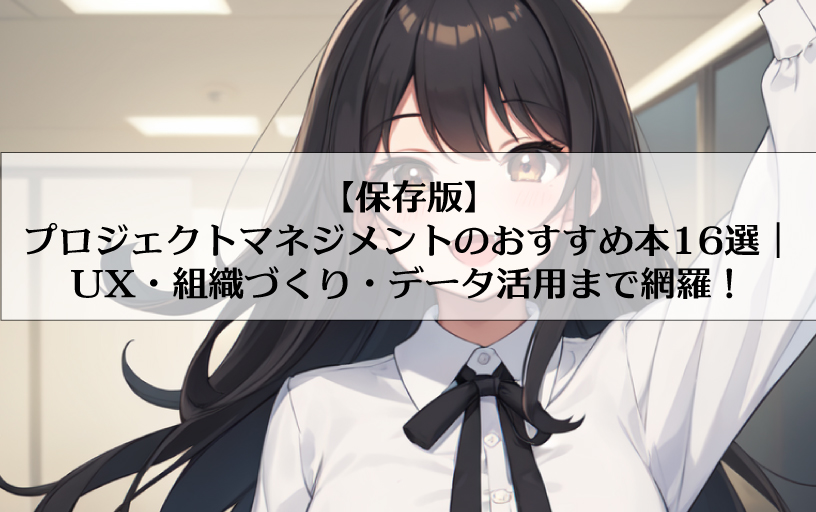

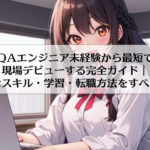
に最も重要なスキル!-PMに必要なホウレンソウとは?-300x200.jpg)
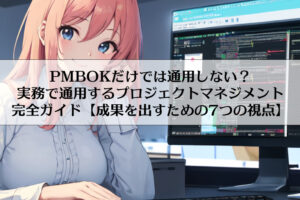
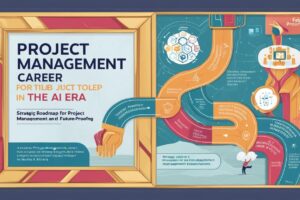




になりたい人へオススメな書籍6選-1-300x200.jpg)