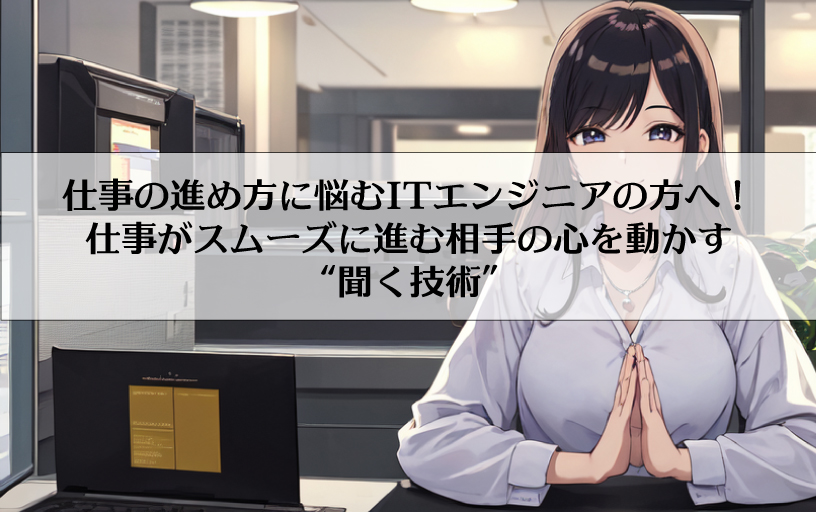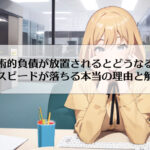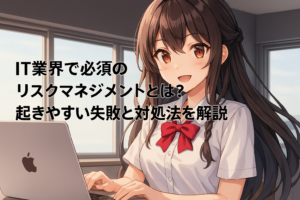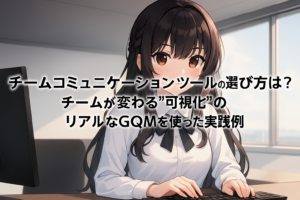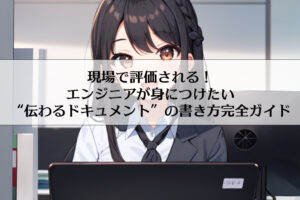はじめに:聞く力がエンジニアとしてのキャリアを変える
ITエンジニアとして働く中で、こんな風に感じたことはありませんか?
「話が噛み合わずレビューがすれ違う」「1on1で何を話していいか分からない」「クライアントの本音が分からず要件が曖昧に進む」――そんなとき、“話す力”の不足を疑うかもしれません。でも実は、多くの原因は“聞く力”にあります。今回は、会話の達人から学ぶ「話を聞き出す技術」をもとに、エンジニアとしての仕事が驚くほどスムーズになる“聞く技術”を6つの視点でご紹介します。
Contents
聞く力はエンジニアの最重要スキルの一つ
聞く力は、エンジニアとしての成果や信頼に直結する最重要スキルの一つです。
なぜなら、ITエンジニアの仕事はコードを書くことだけでなく、設計・レビュー・対話・提案など「相手との意思疎通」が常に求められるからです。たとえ技術力が高くても、相手の意図を汲み取れず、ずれた成果物を出してしまえば評価にはつながりません。逆に、相手の要望を深く理解し、必要な情報を引き出せる人は、信頼されやすく、チームでも重宝されます。
話を聞ける人は「信頼」を得る
聞く力がある人は、相手に安心感と信頼を与えることができます。
特にエンジニアの現場では、専門的な会話が多くなるため、言葉の背景や意図まで丁寧に受け止められる人が貴重です。上司やクライアントが「あ、この人なら話しても大丈夫だ」と思えると、自然と会話の中で本音が引き出せるようになります。それが、認識のズレを減らし、誤解による手戻りやトラブルを未然に防ぐことに繋がります。
「話す力」より「聞く力」が足りていない場面が多い
多くのエンジニアが、「何を言うか」に悩みがちですが、実は「どう聞くか」のほうが重要な場面が多いのです。
要件定義やMTGでの行き違い、レビューですれ違う原因の多くは、“聞いたつもり”による勘違い。相手の言葉を表面的に捉えるだけでは、本質を見逃してしまいます。「話を引き出す技術」では、相手の背景や感情に寄り添いながら“理解”を優先する姿勢こそが、信頼構築と成果に繋がると語られています。
『話を聞き出す技術』から学ぶ6つの実践スキル
「聞く力が大事なのはわかったけど、具体的にどうすればいいの?」
そう感じた方も多いかもしれません。安心してください。本記事では、Podcastの対話現場で実際に培われた『話を聞き出す技術』から、エンジニアが現場ですぐに使える“聞く技術”を6つに分けて解説します。ただの雑談力ではなく、相手の本音や課題を自然に引き出すための“実践的スキル”です。これらを意識するだけで、日々の仕事が驚くほどスムーズになります。
会話で最も重要なのは「理解を最優先にする姿勢」
“質問の内容”よりも、“どれだけ本気で理解しようとしているか”が会話の質を決めます。
エンジニアがやりがちなのは、会話中に「次に何を聞こうか」と考えてしまい、相手の話を上の空で聞いてしまうこと。しかし、相手が本当に伝えたいことは、言葉の裏にある背景や感情に隠れています。『話を聞き出す技術』では、「理解を最優先にする」ことが、最も深く自然な対話を生み出すカギであると強調されています。これにより、的確な返しや適切な質問も自然に浮かぶようになります。
共感と要約で信頼と納得感が生まれる
相手の言葉をそのまま受け取るだけでなく、一度“自分の言葉に変換して返す”ことが信頼構築に直結します。
たとえば、「つまり、〇〇ということですね?」と要約するだけで、「ちゃんと聞いてくれている」という印象を与えられます。また、的確にまとめるには深い理解が必要なので、双方の認識ズレも防げます。このようなやりとりは、1on1やクライアント対応でも非常に効果的で、相手が安心して話せる空気をつくることができます。
質問よりも「会話の流れ」を整えることが重要
聞く技術というと、「うまく質問すること」と考えがちですが、実はその前段階である“会話の流れを整える力”のほうが重要です。
『話を聞き出す技術』では、興味がないまま無理に質問を繋げようとして、相手を困惑させてしまった実体験が紹介されています。話す側が「なんでこの質問?」と感じた瞬間、会話の温度が下がってしまいます。聞きたいこと×話したいことの交差点を意識することこそ、質問力以上に大切なのです。
面接や社内コミュニケーションでの応用例
「聞く技術」が身についてきたら、実際にどのような場面で活かせるのかをイメージしてみましょう。
特にエンジニアにとって、成果に大きく影響するのが“人との接点”です。転職活動の面接、1on1ミーティング、レビュー会議、チームでの設計相談や要件確認――これらはすべて“聞き方”ひとつで結果が変わります。この章では、具体的なシーン別に「聞く技術」の応用方法を紹介し、実践のイメージを持てるように解説します。
面接では「質問力」より「聞く姿勢」が評価される
面接で差がつくのは、“鋭い質問”ではなく“丁寧な理解力”です。
よくある失敗は、テンプレート的な質問を並べてしまうこと。重要なのは、相手が話している内容を丁寧に聞き取り、背景や意図を踏まえたうえで応答することです。たとえば、「それは〇〇のような背景があったからでしょうか?」と一歩踏み込んだ返しができれば、「この人は深く理解しようとしている」と感じさせられます。転職面接では、特に「コミュニケーション力」や「共感力」が重要視されるため、聞く力が評価に直結します。
1on1では「共感と要約」で信頼関係を築く
社内の1on1ミーティングでは、相手が本音を話せる空気をつくることが大切です。
聞く力を活かして「共感+要約」を繰り返すことで、「この人はちゃんと理解しようとしてくれている」と感じてもらえます。たとえば、「それはちょっとプレッシャーでしたよね。つまり、〇〇が難しかったということですか?」と返すだけで、相手は安心して話しやすくなります。そうした安心感が信頼関係を生み、結果的にチームの生産性にもつながります。
会議やレビューでは“ズレ”を防ぎ、誤解を最小限にする
チームでの技術的な話し合いやレビューでは、聞く力が“誤解を防ぐフィルター”の役割を果たします。
特に専門的な会話ほど、言葉の使い方や前提知識にギャップがあるもの。『話を聞き出す技術』の中でも、自分の理解が正しいか確認する「要約・確認フレーズ」が効果的とされています。「つまりこの変更は、パフォーマンス改善が主目的という理解で合ってますか?」のように確認を挟むことで、認識のズレや手戻りを防げます。これは、プロジェクト進行において大きなコスト削減にもつながるのです。
今からできるトレーニング方法
「聞く技術が重要なのはわかったけれど、どうやって鍛えればいいの?」
そう思った方もご安心ください。“聞く力”は先天的な才能ではなく、日常の中で少しずつ鍛えていけるスキルです。しかもその方法は、特別なトレーニングを必要とせず、今日からでも実践できるものばかり。本章では、エンジニアとして日々忙しく働くあなたでも、すぐに取り組める具体的なトレーニング方法を3つご紹介します。継続することで、自然と会話の質が変わっていくのを感じられるはずです。
会話や動画を「背景まで考えながら聞く」
何気ない会話や動画コンテンツも、“背景を読み取る練習材料”に変えることができます。
ただ情報を聞き流すのではなく、「なぜこの人はこの言い方をしたのか?」「どんな価値観や経験があるのか?」を想像することで、相手の意図を読み取る力が育まれます。特にPodcastやインタビュー系YouTubeは最適で、話し手の感情や文脈を意識して聞くと、普段見過ごしていた“行間”が見えるようになります。これは面接や1on1など、相手との対話で活きる非常に実践的な力になります。
要約練習は「理解の証明」として効果的
「聞いた話を自分の言葉で要約する」練習は、理解力・共感力・表現力のすべてを鍛える一石三鳥の方法です。
会話の終わりやMTG後に、「つまりこういうことですね」とまとめてみるだけで、理解が深まると同時に相手との認識ズレを防げます。1人での練習でも、読んだ記事や観た動画の内容をTwitterやメモアプリで要約するだけで十分。自分の理解を“外に出す”ことで、聞いた内容が定着し、応用力が身につきます。
知識のインプットが質問力・好奇心を支える
聞く力の土台には、実は「知識」と「興味の幅」が大きく関わっています。
知らない話には質問も湧きません。だからこそ、自分が苦手な分野の本を読んだり、相手の職種について軽く調べたりするだけでも、会話に深みが出てきます。『話を聞き出す技術』でも、ゲストの分野について事前に本を読むなど、インプットを重視する姿勢が語られていました。好奇心は“無知を自覚したとき”に生まれ、知識の空白が会話への関心を高めてくれます。
Q1. 「聞く力」は話し上手になるためにも役立ちますか?
はい、間違いなく役立ちます。聞く力があれば、相手の興味や感情の動きを捉えた返しができるため、自然と会話が弾むようになります。話す前に、まず相手の話にしっかり耳を傾けることが、話し上手への第一歩です。
Q2. チームに聞く力がある人が一人いると、どんな変化が起こりますか?
会議やチャットでの意見交換がスムーズになり、メンバーの本音や懸念点が自然と共有されるようになります。結果として、チーム全体の心理的安全性が高まり、協力体制も強化されていく傾向があります。
Q3. 自分では聞いているつもりでも、相手から「伝わっていない」と言われるのはなぜですか?
ただ黙って聞くだけでは、相手に“聞いてもらえた”という安心感は伝わりません。相槌や要約など、聞いた内容を受け止めて返す行動が伴って初めて、相手は理解されたと実感できます。
Q4. 初対面の人に対しても聞く力は通用しますか?
はい、むしろ初対面だからこそ効果を発揮します。表面的な会話ではなく、相手の価値観や経験に触れようとする姿勢は、強い信頼感を生み出します。相手の話に深く関心を示すことが距離を縮める鍵です。
Q5. オンラインミーティングでも聞く力を発揮できますか?
もちろんです。特にオンラインでは、表情や声のトーンに敏感になり、リアクションや確認を丁寧に行うことで、対面以上に深いコミュニケーションを築くことができます。視線やうなずきも重要です。
Q6. 聞く力は人見知りでも身につけられますか?
はい、大丈夫です。むしろ人見知りの方は無理に話すことが少ない分、相手の話をしっかり聞こうとする傾向があります。意識的に相手の話に集中する姿勢を持つことで、自然と聞く力は伸びていきます。
Q7. 「聞く力」があると評価される具体的な場面はどんなときですか?
顧客からのヒアリング、仕様調整の交渉、チーム内の問題共有など、相手の意図を正確に汲み取って対応できたときに、特に評価されます。的確な質問や理解の深さが評価につながります。
Q8. 聞く力を鍛えるために避けた方がよい習慣はありますか?
会話中にスマホを触ったり、相手の話を途中で遮るクセは避けましょう。また、自分の意見をすぐに述べたくなる場面でも、まずは最後まで話を聞くことを意識することで聞く力は鍛えられます。
Q9. 一方的に話す人に対しても聞く力は有効ですか?
はい、有効です。一方的な話の中でも、要点を見極めて整理したり、適切なタイミングで質問を挟むことで、相手自身も考えを言語化しやすくなります。会話の質を高める調整役にもなれます。
Q10. 聞く力が身につくと、仕事以外でもメリットがありますか?
あります。プライベートな人間関係でも、信頼されやすくなり、相談される機会が増えることもあります。また、相手を理解する力が高まることで、無用な誤解や衝突を避けられる場面が増えていきます。
まとめ
「聞く力」は、エンジニアとしての仕事を円滑にし、信頼される存在になるための重要なスキルです。本記事では、実践的な6つの聞き方から、日常でできるトレーニング方法、面接や社内での応用までを紹介しました。聞く力は、才能ではなく“習慣”で伸ばせるスキルです。だからこそ、今日から意識して少しずつ育てていきましょう。そして、そのスキルを活かせる環境や働き方に悩んでいる方は、ぜひ一度キャリア相談もご活用ください。新たな一歩が、きっと見つかるはずです。
さいごに:スタートアップで“聞く力”を武器にしたいあなたへ
この記事を通してお伝えしてきた「聞く力」は、単なるスキルではなく、**新しい環境でも信頼される人材になるための“武器”**だと私は考えています。
もしあなたが、
「もっと裁量のある環境で自分の力を試したい」
「スピード感のあるチームで本質的なコミュニケーションを武器にしたい」
そう思っているなら、スタートアップへの転職は選択肢として本当におすすめです。
中でも私が信頼してご紹介できるのが、フォースタートアップスさんです。
スタートアップ領域に特化し、これまで1,200名以上のCxO・経営幹部クラスの転職を支援してきた実績があり、年収1,000万円以上の事例も豊富。
現場を知るキャリアパートナーが、あなたの想いやスキルをしっかり聞き、最適な提案をしてくれます。
もちろん、非公開のハイクラス案件も多数取り扱っています。
「今すぐ転職」じゃなくても構いません。
これからのキャリアを真剣に考えたい方は、一度話を聞いてもらうだけでも大きな一歩になるはずです。