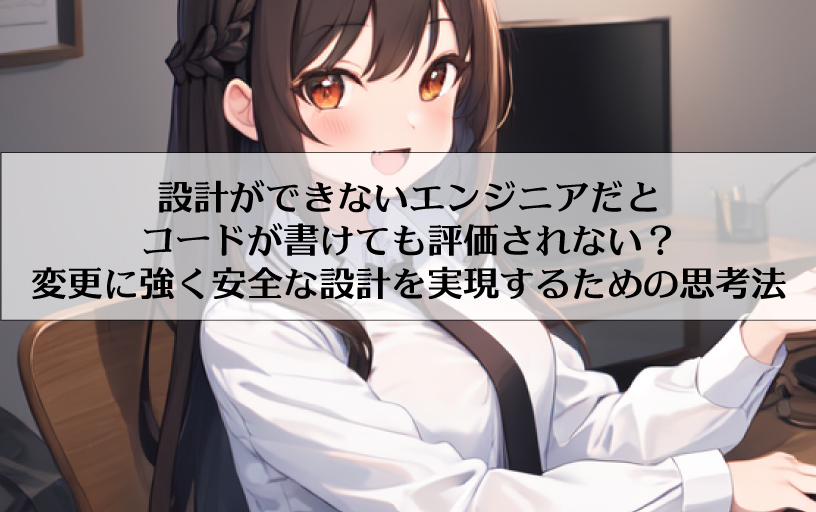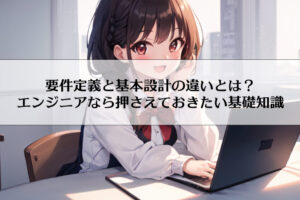こんにちは!ITキャリアのプロです!

設計が苦手なエンジニア、もしくは設計を“なんとなく避けている”エンジニアは意外と多いものです。コードは書けるのに、なぜか評価されない。そんな状況に心当たりはありませんか?
実は、今の開発現場や転職市場で重視されているのは、「ただ動くコード」ではなく「変化に強く、安全に運用できる設計」ができるかどうか。設計力は、あなたのキャリアを支える“思考の技術”です。この記事では、設計に苦手意識を持つエンジニアが押さえておくべき思考法と実践ステップを、やさしく丁寧に解説していきます。
Contents
なぜ「設計」がエンジニアの仕事の本質なのか?
「設計」と聞くと、まだコードも書けない自分には縁がないと思っていませんか?実はその考えこそが、成長を遠ざける落とし穴です。本章では、なぜ設計がエンジニアにとって“単なる手段”ではなく“本質的な仕事”なのか、根本から紐解いていきます。読むことで、「今の自分」に必要なスキルが何か見えてくるはずです。
設計とは「未来の変更に備えること」である
設計とは「今」だけでなく「未来」を見据えてコードをどう変えやすくするかを考える仕事です。
ソフトウェアは一度作って終わりではなく、常に変更され続けるものです。
良い設計は変更が楽で安全であり、事業方針の変更・ユーザー要望・技術進化など、変化が絶えない現代の開発において、設計は生きた資産になります。未来に起こりうる変更を想定しておくことが、設計の本質です。
「良い設計」は変更を楽にし、「悪い設計」は成長を止める
設計の良し悪しが、自分自身の成長スピードに直結します。
良い設計は変更を安全に行えるため、改善や学びの反映がしやすくなります。
ドメイン理解が深まったとき、または新しい技術が導入されたとき、柔軟な設計であればすぐに対応できます。逆に設計が悪いと、改修時に多くの手戻りやバグを引き起こし、「直したくても直せない」状態に陥ります。設計は単にコードの構造を決めるものではなく、自分自身の成長の器でもあります。
開発者の設計力が事業成長を左右する
設計力のあるエンジニアがいるチームは、事業の変化に強く、スピーディに成長できます。
設計によって変更コストが抑えられれば、開発スピードも、方向転換の柔軟性も上がります。
ソフトウェアの変更が楽で安全であれば、事業活動の変化のスピードを上げられます。設計がボトルネックになっていると、組織はチャンスを逃しやすくなります。つまり、エンジニアの設計スキルは、単にコードのためではなく、ビジネスのために求められています。
「設計できないエンジニア」に共通する3つの誤解
設計に苦手意識を持つエンジニアの多くは、「そもそも設計って何?」という根本的なところでつまずいています。そして、その背後には“誤った思い込み”が潜んでいることが少なくありません。この章では、設計できない状態に陥ってしまうエンジニアが抱えがちな3つの誤解を明らかにし、その誤解をどう乗り越えるべきかをお伝えします。
「とりあえず動けばいい」は設計ではない
設計とは「とりあえず動くもの」を作ることではありません。
動作することと、将来の変更に対応できることはまったく別のスキルです。
今動くコードを素早く書けても、次の仕様変更で破綻するようでは設計とは言えません。設計とは、未来の拡張や修正を安全かつ楽に行えるように構造を作ることであり、動作するコードを書くこととは目的が異なります。
「設計=図を書くこと」だと思っていないか?
設計は「図面」ではなく、「思考の構造化」です。
設計書やクラス図を書く行為はあくまで手段であり、本質はどう分けるかを考えることにあります。
責務の分離や意味のあるまとまりを作ることが大切です。設計とは、システムの目的と制約を理解し、適切な単位で構成要素を分けることです。それは図やテンプレートでは代替できない、深いドメイン理解と思考の結果です。
変化を考慮しないコードは、すぐに技術的負債になる
設計を怠ったコードは、時間と共に技術的負債となって返ってきます。
設計されていないコードは、修正や追加のたびに複雑さが増し、保守コストを急激に引き上げます。
設計がやっかいで危険になると、学びと成長の機会が減ってしまいます。設計を放棄すると、いつしかそのコードに手を加えることすら恐ろしくなり、新しい技術の導入や改善が止まってしまいます。
「変更に強く、安全な設計」を実現するための思考法
「設計が大事なのはわかった。でも、どうやって“変更に強く、安全な設計”を実現すればいいの?」──これは多くの若手エンジニアが抱える疑問です。なんとなく設計しているうちは、その“強さと安全さ”は手に入りません。この章では、実践的な設計の原則をもとに、設計力を本質から鍛えるための3つの思考法を紹介します。
設計のゴールは「成長に耐えられる構造」を作ること
設計の目的は“今を最適化すること”ではなく、“将来の成長を支える構造”を作ることです。
ビジネスや技術、ユーザーのニーズは常に変わるため、未来の変化に耐えられる柔軟性が求められます。
短期的な納期に追われて場当たり的な構造を組んでも、すぐに限界が来てしまいます。逆に、成長を見越した設計ならば、チームもサービスも持続的に発展できます。
責務を「分ける」ことが設計の核心
良い設計は「責務の明確な分離」から生まれます。
責務が曖昧なままでは、コードがどんどん複雑化し、変更のたびに他の場所へ影響を及ぼします。
設計では常に「これはどの役割か?」「何に依存すべきか?」を問い続ける必要があります。表示ロジックと業務ルールが混在していると、どちらかの変更時に両方を壊してしまうリスクが高まります。役割を切り分けることで、部分的な変更でも安全に対応できる構造が作れます。
「意味のあるまとまり」でモデルをつくる
クラスや関数は“技術的都合”ではなく、“意味のまとまり”で構成すべきです。
業務の文脈と設計が一致していないと、コードが読みづらく、誤解やバグの温床になります。
設計は、理解をコードに反映する作業です。業務の概念やドメインを正しくモデリングし、それに基づいて設計することで、コードは意味を持ち、他の開発者にも伝わりやすくなります。
クラス設計は“理解のモデル化”である
「クラス設計」と聞くと、“綺麗な構造”や“再利用できる部品”をイメージするかもしれません。
しかし、クラス設計の本質はそこではありません。
クラスとは、あなたが理解した世界をどう切り取り、どう表現したかの“認知の反映”なのです。
この章では、クラス設計がただの技術ではなく「思考のモデル化」であることを、実践的に紐解いていきます。
設計とは“モデル”をつくること
クラス設計の本質は、現実世界や業務の仕組みを“モデル”としてソフトウェア上に表現することです。
モデルは開発者の理解を形にし、プログラムが何を意味しているかを他人にも伝えるための手段です。
設計はただのクラスの配置ではなく、業務や仕組みの本質的な構造をつかみ、それをどう切り出すかの選択です。それが“モデルをつくる”という行為であり、設計力とはつまり“理解力”そのものです。
業務ドメインをどう捉えるかが設計品質を決める
クラス設計の良し悪しは、業務のドメイン(領域)をどれだけ深く正確に捉えているかで決まります。
ドメインの構造やルールを的確に把握できなければ、現実を反映した設計ができません。
業務理解が変わることさえ設計変更の要因になります。つまり、「そもそも正しく理解していないまま作った設計」は、後で必ず破綻します。クラス名や属性、振る舞いの設計は、すべてドメイン理解のアウトプットです。
「現場で使える」設計とは何か?
現場で役立つ設計とは、“変更に耐えられて、理解しやすい設計”です。
チームで開発する以上、設計は自分だけが理解していても意味がなく、他人にとっても「読めて、変えやすい」ことが求められます。
クラスや構造を「そう設計する理由」が他人にも伝わるように設計されていれば、開発のスピードも、品質も上がります。現場で使える設計とは、「思考の結果がにじみ出ている設計」であり、それこそが設計スキルの成熟を示す指標です。
どうすれば設計ができるようになるのか?若手が実践すべき訓練法
「設計が大事なのはわかる。でも、自分にはまだ早いかもしれない…」そう感じていませんか?
設計は一部の上級者だけのスキルではありません。むしろ、若手のうちから“設計的思考”を持てるかどうかで、数年後のエンジニアとしての成長速度が大きく変わります。
ここでは、初心者〜若手エンジニアでも今すぐ実践できる「設計力を育てる3つのトレーニング法」を紹介します。
実装の前に「考える時間」をつくる
コーディングの前に、必ず“構造を考える時間”を持ちましょう。
設計とは「作る前にどう作るかを考えること」であり、思考なしに書かれたコードは再利用性も保守性も損なわれます。
エディタを開く前に紙やホワイトボード、あるいはテキストで構造の仮設を描いてみることが有効です。「どういう責務が必要か」「依存関係はどうあるべきか」を思考し、見える形にするだけで設計力は一歩前進します。
「他人のコード」を読んで設計意図を学ぶ
設計力を高めるには、自分のコードだけでなく“他人の設計”にも触れることが不可欠です。
他人がなぜそのようなクラス構造や責務分離をしたのかを読み解くことは、自分の設計眼を育てます。
コードレビューの際や、オープンソースのリポジトリを読むとき、「なぜこのように設計したのか?」を意識的に追うことで、現実的で優れた設計パターンを吸収できます。
レビューで“設計の対話”を重ねよう
レビューは「バグ探し」ではなく「設計を言語化して伝える訓練の場」です。
自分の設計意図を他人に伝え、フィードバックを受け取る過程で、設計力は飛躍的に伸びます。
「なぜこういうクラス構造にしたのか」「この責務分離にどういう意図があるのか」などを明確に語れることは、設計が偶然ではなく必然であることの証です。設計を言葉にする習慣が、設計力を加速させます。
設計力がエンジニアの市場価値を決める時代
「とりあえず動くコードを書ければ十分」──そんな時代はもう終わりました。
今、企業がエンジニアに求めているのは「ただの作業者」ではなく、「変化を見据え、設計できる思考者」です。
この章では、設計力がなぜ現代エンジニアにとって“武器”になるのか、そしてキャリアや転職にどのような影響をもたらすのかを解説します。
「設計できる人」は転職市場でも重宝される
設計力のあるエンジニアは、企業からの評価が高く、選ばれる立場になれます。
設計ができる人材は、単にコードを書く人ではなく、システム全体を考えられる“上流の人材”と見なされます。
転職市場では、設計スキルを持つエンジニアが即戦力として評価され、求人票にも「設計経験」が明記されるケースが増えています。プロダクトの将来性やチームの成長性を支えられる“構造をつくれる人”が求められているのです。
設計力=チームを導けるスキル
設計ができるエンジニアは、技術的にもチーム運営的にも“リーダー”になれる存在です。
設計は技術選定・アーキテクチャ構築・役割分担など、チーム全体の方向性に関わる意思決定を含みます。
設計力があると、開発が迷子にならず、メンバーが安心して動ける環境をつくれます。設計は個人の能力にとどまらず、チームの質と成果を左右する根幹スキルなのです。
「思考の型」としての設計スキルをどう磨くか
設計は一部の天才だけが持つ才能ではなく、誰もが“型”として学べるスキルです。
設計には一定の考え方や原則があり、それを繰り返し実践することで思考が習慣化されていきます。
「変更に強い構造をどう作るか」「責務をどう分離するか」といった問いに対して、自分なりの解を持てるようになることが設計スキルの第一歩です。思考のフレームワークとして設計を捉えることで、再現性のあるスキルとしてキャリアに活かすことができます。
よく聞くご質問
Q1. 設計書を書かないと設計したことにならないのでしょうか?
いいえ、設計書の有無だけで設計が成り立つわけではありません。設計とは、本質的には「どう作るべきか」を整理し、構造的に考える行為です。ドキュメントはその一部を可視化する手段に過ぎません。
Q2. 設計を考える時間がもったいなく感じてしまいます。
設計に時間を使うのは一見遠回りに見えるかもしれませんが、長期的には手戻りやバグの削減につながる最短ルートです。考えずに書いたコードほど、後で高くつくことを多くの現場が実感しています。
Q3. 設計力はセンスが必要だと感じていますが、努力で身につきますか?
設計力はセンスではなく思考の習慣です。最初は難しく感じても、日々の開発の中で意識的に構造を考えることで確実に上達していきます。誰でも訓練次第で伸ばせるスキルです。
Q4. 現場がスピード重視なので設計をする余裕がありません。
スピード重視の現場だからこそ、設計の重要性が高まります。設計がなければ、変更やトラブル対応に時間を奪われることになり、結果的にチームの生産性が下がってしまいます。
Q5. 設計をレビューしてもらうと「正解がわからない」と言われがちです。
設計に絶対的な正解はありませんが、「なぜこう分けたのか」「なぜこの構造にしたのか」を言語化できる設計は、納得されやすくなります。意図を伝えること自体が設計力の一部です。
Q6. 業務知識が浅くても設計はできるのでしょうか?
可能ですが、より深い業務理解があるほど質の高い設計になります。設計とは、業務の流れやルールをどうソフトウェアに落とし込むかの作業でもあるため、理解が設計の土台になります。
Q7. 設計より実装の方が評価されやすい気がします。
目に見える成果として実装が評価されがちですが、設計はその実装の土台を支えるものです。長期的に成果を出し続けられるエンジニアほど、設計の重要性を理解し、評価もされていきます。
Q8. 設計経験がなくても転職に不利にはなりませんか?
実装経験しかない段階でも問題はありませんが、設計への意識や学ぶ姿勢があるかは面接で見られます。設計を意識した開発ができると、より上流のポジションへの道も開けやすくなります。
Q9. フレームワークが設計をある程度やってくれるのでは?
フレームワークは便利な初期構造を提供してくれますが、業務に特化したロジックの設計までは担ってくれません。自分の設計判断が求められる場面は、必ず出てきます。
Q10. 設計が好きになれません。どう向き合えば良いですか?
設計は「正解を出す作業」ではなく「どうすればもっと良くなるかを考える過程」です。慣れるまでは難しく感じますが、自分なりの改善を積み重ねる中で楽しさが見えてくることもあります。
まとめ:設計できるエンジニアは“変化を味方にできる”
ここまで「設計できないエンジニア」が陥りやすい落とし穴や、設計力を伸ばす思考法・訓練法を解説してきました。
最後に改めて強調したいのは、“設計力とは、変化を恐れずに受け入れられる力”だということです。
この章では、エンジニアとしてのキャリアを長期的に成功させるために、設計力が持つ本質的な価値をまとめます。
変化に強い設計は、変化を成長に変える
設計力があると、変化がチャンスになり、経験が武器になります。
設計とは、変化を前提にした構造をつくる行為であり、変化が訪れるたびに設計の真価が問われます。
設計できる人は変化に巻き込まれるのではなく、それを制御し、味方にできる立場へと自然に成長していきます。
設計は“実装力”ではなく“理解力”で磨かれる
設計力を伸ばすには、コードを書くこと以上に“業務や課題を理解する力”が必要です。
設計とは、現実世界の仕組みやルールを正確にモデル化し、コードに落とし込む作業です。
「なぜこのような処理が必要なのか?」「何を守るべきルールなのか?」を考え抜く姿勢こそ、設計力を磨く鍵です。
設計力はあなたの“キャリア資産”になる
設計力は、技術トレンドが変わっても色褪せない、エンジニアの本質的なスキルです。
設計力は単なる言語やフレームワークの知識ではなく、構造的に問題を捉えて整理する“思考の技術”です。
アーキテクト、テックリード、PdMなど、どんなキャリアパスでも設計の素養は強力な武器になります。学び続ける価値のあるスキルとして、若手のうちから“設計力”を意識して伸ばしていきましょう。
管理人おすすめ:本気でキャリアを変えたいエンジニアに紹介したいエージェント
設計力を身につけ、現場での信頼を獲得し、市場価値を高めていく──その先にあるのが、「もっと挑戦できる環境」や「本当に価値を発揮できる職場」へのキャリアアップです。
もし、今の環境で自分の設計力や思考力が十分に活かせていないと感じているなら、スタートアップでの挑戦も選択肢の一つかもしれません。
そこで私が自信を持っておすすめしたいのが、フォースタートアップスという転職支援サービスです。
スタートアップへのハイクラス転職なら、フォースタートアップス
スタートアップと向き合い続けてきた専門のエージェントだからこそ、**「変化を味方にしたいエンジニア」**にぴったりのフィールドを紹介してくれます。
- スタートアップ特化の専門家が、あなたの強みを丁寧に引き出し、マッチする企業を提案
- これまでに1,200名以上のCxO・経営幹部クラスの転職支援実績
- 年収1,000万円超の高年収転職事例も多数あり
- 公開されていないハイクラス求人も豊富に保持
「今の自分ではまだ足りない」と感じているあなたこそ、次のステージに進む準備ができているはずです。
まずは気軽にキャリアの壁打ち相談から始めてみてください。