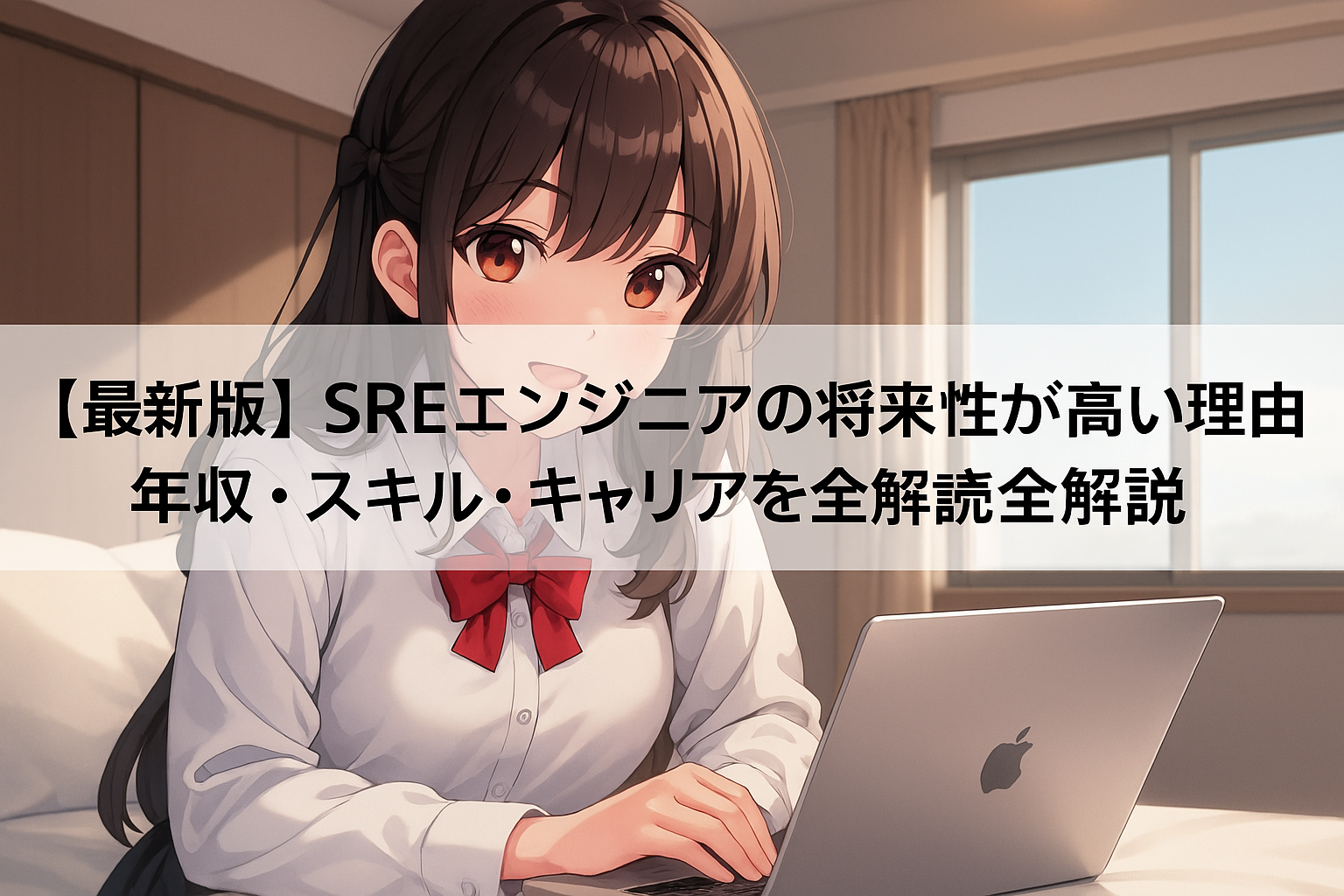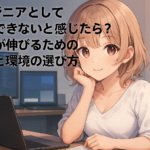こんにちは!ITキャリアのプロです!

「SRE(Site Reliability Engineer)って最近よく聞くけど、実際どんな仕事?」「将来性はあるの?」そんな疑問を持つ若手エンジニアの方に向けて、この記事ではSREの全体像をわかりやすく解説していきます。仕事内容、必要なスキル、年収、やりがい、そして未経験から目指す方法まで、まるっと網羅。これからのキャリアを考えるうえで、SREという選択肢がどんな未来につながるのか、一緒に見ていきましょう。
Contents
SREってなに?エンジニア初心者にもわかるやさしい解説
「SREって名前は聞いたことあるけど、実際どんなことするの?」
「インフラエンジニアや運用担当とどう違うの?」
そんなふうに思っている方も多いはずです。難しそうに見えるかもしれませんが、SREの考え方はとてもシンプルです。ここでは、初めて聞く人でもすっと理解できるように、SREの役割をわかりやすく解説していきます。
一言で言うと「サービスの信頼性を守る人」
SREとは「Site Reliability Engineer(サイトリライアビリティエンジニア)」の略で、簡単に言うと「サービスが安定して動くように支えるエンジニア」のことです。
たとえば、ユーザーがアプリを使っているときに、エラーが出たり、突然つながらなくなったりしたら困りますよね?そうならないように、裏側でシステムの状態を監視し、必要に応じて改善していくのがSREの仕事です。
しかもただの“監視役”ではありません。SREはコードを書いて、自動で障害を検知・復旧する仕組みを作ったり、チーム全体の開発フローをより良くしたりもします。
SREは「運用するだけ」じゃないのがポイント
よく「SREって運用エンジニアでしょ?」と言われることがありますが、それはちょっと違います。
SREは**“信頼性をエンジニアリングで実現する”**のが役割です。
従来の運用エンジニアは、どちらかというと手動での対応が中心でしたが、SREは違います。
トラブルが起こるたびに人が対応するのではなく、「同じ問題が起きない仕組み」を作ることにフォーカスしています。
この考え方が、「SRE=次世代の運用エンジニア」と呼ばれる理由です。
開発チームの一員として、サービスの未来を支える
SREはインフラだけを見るポジションではありません。
実際には、開発チームやプロダクトオーナーとも連携しながら、サービス全体の品質やスピードにも関わっていきます。
たとえば、「新しい機能をリリースするとき、どうやって安全に出せるか?」とか、「トラフィックが急増したらどう対応するか?」といった課題にも向き合います。
つまり、SREは単に裏方ではなく、サービスの価値を最大化するパートナーのような存在。若手エンジニアにとっては、技術もビジネスも学べるとても魅力的なロールなんです。
なぜ今SREが注目されているの?時代背景と企業ニーズを解説
SREという仕事が広く知られるようになったのは、ここ数年のこと。でも「なんで急に話題になってるの?」と不思議に思っている人も多いのではないでしょうか。実はその背景には、ITサービスを取り巻く環境の急激な変化があります。SREが今、注目されている理由を、時代の流れと企業のニーズからひも解いてみましょう。
サービス停止は“信用の損失”につながる時代に
今の時代、アプリやWebサービスが「いつでも使えること」は当たり前になっています。
だからこそ、数分でも止まってしまえば、ユーザーの信頼を一気に失ってしまうことも。
特に、ECや金融系のサービスでは、1分の停止が何百万円もの損失になるケースもあります。
そうした状況を受けて、多くの企業が「止まらないサービス」を目指すようになりました。
そこで頼りにされるのが、サービスの安定稼働を支えるSREという存在です。
技術的にも、ビジネス的にも、SREはまさに“なくてはならない役割”として注目を集めています。
クラウド化・マイクロサービス化が進み、運用の複雑さが増した
以前は、オンプレミスで物理サーバーを管理していた時代。
でも今は、クラウドを使って柔軟にスケールするアーキテクチャが主流です。
さらに、マイクロサービスの普及で、システム全体の構成がどんどん複雑になっています。
この変化により、「障害が起きたら誰がどう直すか」「リリース後に何が起こるか」を正しくコントロールするのが難しくなりました。
SREは、こうした複雑なシステム環境を前提に、安定運用の仕組みを設計・改善する専門職。
時代のテクノロジーが進化するほど、SREの価値がより際立つようになっているんです。
“開発も運用も”の時代。SREがその橋渡し役に
これまで、開発と運用は別チームで行うのが普通でした。
でも最近では、「DevOps」という言葉に代表されるように、開発と運用の垣根をなくし、協力してサービスを作っていく流れが一般的になっています。
この中で、SREは「信頼性」という視点から開発チームと連携し、よりよいサービスづくりを支える役割を担います。
「ただの運用担当」ではなく、サービス全体に深く関わる技術職として、今の時代にフィットしているのがSREなんです。
SREエンジニアの主な仕事内容|他職種との違いもサクッと理解
「SREって実際にはどんな仕事をしてるの?」
「インフラエンジニアやDevOpsとどう違うの?」
そんな疑問を持っている方に向けて、ここではSREエンジニアの代表的な業務内容を整理しながら、他の職種との違いもやさしく解説していきます。これを読めば、SREのポジションがどんな特徴を持っているのかがイメージしやすくなるはずです。
主な仕事は「信頼性を保つための仕組みづくり」
SREの仕事は、一言で言うと「サービスが安定して動き続ける仕組みをつくること」。
たとえば、こんな業務を日々行います。
- サービスのモニタリング(障害や遅延の検知)
- 障害時のトラブルシューティング
- 再発防止の自動化スクリプト作成
- リリースやデプロイの改善(CI/CDの最適化)
- SLO(Service Level Objective)の設計と運用
特徴的なのは、運用だけでなく、問題解決のためにコードを書くことも日常的にあるという点。
トラブルが起きた原因を探し出し、同じことが起きないように設計を変えたり、ツールを開発したりすることがSREの価値です。
インフラエンジニア・DevOpsとの違いは「目的の明確さ」
インフラエンジニアやDevOpsとSREの仕事内容は、部分的に似ている部分もあります。
ただし、大きな違いは「信頼性を最優先にしているかどうか」という点です。
インフラエンジニアは、サーバーやネットワークの構築・保守が主な業務です。DevOpsは開発と運用の協働を進める文化的なアプローチ。
一方SREは、「ユーザーにとって快適なサービスを、どれだけ安定して提供し続けられるか」を目的に、システム全体を設計・改善していきます。
技術的なタスクは似ていても、考え方や意思決定の基準がSRE独特なんです。
自動化がカギ。だからこそ「コードが書ける運用担当」
SREが他職種と大きく違うのは、「手動対応を最小限にし、どんどん自動化していく」という文化を持っていることです。
たとえば、「毎週手作業でログを確認して障害対応していた」ような業務があったとします。
SREは「それって自動でできるようにしよう」と考え、ツールを作ったりスクリプトで対応したりします。
つまり、**「運用もするけど、むしろ改善がメイン」**なのがSREです。
「運用エンジニアなのに、開発にも関われる」。
このユニークな立ち位置が、SREという職種の魅力でもあります。
SREエンジニアの年収とキャリアパス|本当に稼げるの?
「SREって難しそうだけど、そのぶん年収は高いの?」
「キャリアとして長く続けられる仕事なのかな?」
スキルアップを考えている若手エンジニアにとって、年収やキャリアの見通しはとても大切なポイントです。ここでは、SREエンジニアのリアルな待遇感と、将来的なキャリアの広がりについてご紹介します。
SREの年収は、エンジニア職の中でも高水準
SREエンジニアの年収は、全体的にかなり高めの傾向にあります。
企業によって幅はありますが、20代後半で500〜700万円台、30代になると800万円以上を狙えるケースも少なくありません。
その理由は、SREが「サービスの安定性」というビジネスの根幹を支える職種だから。
実際、システムトラブルによる損失が大きい企業ほど、SREへの投資を惜しまない傾向にあります。
さらに、インフラ・開発・運用のすべてに精通している必要があるため、スキルの幅広さ=市場価値の高さにもつながっています。
キャリアパスは複数。専門を極めるもよし、横展開もあり
SREとして経験を積んだあとのキャリアパスは、想像以上に多彩です。
代表的なのは、以下のようなパターンです:
- シニアSRE:大規模なサービスの設計や、チーム全体の信頼性戦略を担う
- SREマネージャー:チームビルディングや人材育成、プロジェクト推進をリード
- プラットフォームエンジニア:SREよりも開発寄りに寄った技術基盤の構築を担当
- CTOやVPoE:スタートアップや新規事業で技術責任者として活躍
また、信頼性を設計するという視点は、セキュリティやプロダクトマネジメントの分野にも応用が利くため、職種の枠を超えてステップアップしやすいのも特徴です。
フリーランスや副業としても価値が高まっている
最近では、SREのスキルを活かして副業やフリーランスで働く人も増えています。
SREの仕事は「構築して終わり」ではなく、「継続的な改善」がメインなので、一定の信頼を築けばリモートでの稼働や業務委託も十分可能です。
とくにクラウドの知識やIaC(Infrastructure as Code)のスキルがあると、月単価80〜100万円以上の案件も見つかることがあります。
時間や場所にとらわれず、自分のペースで働きたいと考えるエンジニアにとって、SREは相性の良い選択肢と言えるでしょう。
未経験からSREになるには?必要なスキルと学習ロードマップ
「SREってスゴそうだけど、未経験からでもなれるのかな…?」
「どんなスキルが必要なのか、何から勉強したらいいのかわからない」
そんな不安や疑問を感じている若手エンジニアの方に向けて、SREを目指すために必要なスキルや、学習のステップを丁寧にお伝えします。実は、未経験でも着実に目指せるルートがあるんです。
まずは「インフラの基本知識」をしっかりおさえる
SREを目指すなら、まず身につけたいのがインフラの基本的な知識です。
クラウドやネットワーク、OS、コンテナなど、サービスを支える土台を理解することで、SREとしての第一歩を踏み出せます。
具体的にはこんな内容がおすすめ:
- Linuxの操作やコマンドライン
- ネットワークの基礎(TCP/IP、DNSなど)
- クラウド(特にAWSやGCP)の基本サービス
- コンテナ技術(Docker、Kubernetesなど)
これらは入門書やオンライン講座でも学べる範囲なので、文系出身や非ITからのキャリアチェンジでも問題なしです。
次に「コードで運用を改善するスキル」を伸ばす
SREはただの運用担当ではなく、「コードで仕組みを改善する人」です。
だから、ある程度のプログラミングスキルも必要になります。
といっても、最初から高度な開発スキルが求められるわけではありません。
まずはこのあたりから始めるのが◎:
- ShellスクリプトやBashでの自動化
- PythonやGoなどの運用に強い言語
- インフラのコード化(Terraform、Ansible など)
コードを書いて効率化するのが面白いと思えるタイプの人には、SREはかなり向いていると言えます。
学習ロードマップの一例:0からSREまで
未経験からSREを目指すなら、以下のようなステップで進むとスムーズです。
- IT基礎:ネットワーク/サーバー/Linux/クラウドの基本を理解
- プログラミング:Shell/Python/Gitなどで簡単な自動化を体験
- インフラ構築の実践:DockerやTerraformを使って環境を作る
- 監視と運用の知識:Prometheus/Grafana/SLOなどの学習
- 開発との連携や改善視点:DevOps/CI/CDの流れを学ぶ
このステップを意識して、1年かけてじっくり取り組めば、未経験でもSREとして十分に活躍できるレベルに到達可能です。
実際どう?SREエンジニアのやりがいとしんどさ【本音トーク】
「SREってかっこよさそうだけど、実際の現場ってどうなんだろう?」
「やりがいはありそうだけど、ぶっちゃけ大変そう…?」
そんなリアルな疑問に答えるべく、ここではSREとして働くうえで感じやすい「やりがい」と「しんどさ」について、包み隠さずお話しします。良い面も、大変な面も、どちらも知ったうえで判断してほしいからです。
やりがい①:サービスを“裏側から支える”手応えがある
SREの大きな魅力は、「自分の仕事がサービスの安定運用につながっている」と、実感しやすいことです。
たとえば、自分が設計した仕組みで障害が起きなくなったとき、ユーザーから「安定してるね」と言われたとき。そんな瞬間に強い達成感を感じる人は多いです。
また、改善や自動化の提案がそのまま採用されることも多く、自分の意見がちゃんと価値になる環境もポイント。
目立つ仕事ではないかもしれませんが、“技術で支える裏方”のプロとして、誇れる役割を担えます。
やりがい②:技術の幅が広がり、自分の成長を感じられる
SREは開発・インフラ・自動化・監視など、幅広い技術領域に関わります。
最初は覚えることが多く感じるかもしれませんが、そのぶんどんどんスキルが増えていく感覚があります。
インフラに強いけどコードも書ける、CI/CDの設計もできるし、障害対応も任せて。
そんなふうに、自分の引き出しが増えていくことで、技術者としての市場価値も自然と高まっていきます。
いつの間にかチームで頼られる存在になっていたという声も多い職種です。
しんどさ:トラブル時のプレッシャーと、求められる責任の重さ
SREとして大変なのは、「障害対応時のプレッシャー」です。
システムに何かトラブルが起きたとき、最前線で原因を探し、早急に対応しなければならない場面があります。
特に本番環境に影響が出ている場合は、チーム全体がピリつくこともあり、冷静な判断力とコミュニケーション力が求められます。
また、仕組みで解決する文化がある反面、すぐにでも直してほしいという短期的な期待とのギャップに悩むことも。
こうした経験を乗り越えることで、エンジニアとしての自信も深まっていくのがSREという仕事でもあります。
まとめ|SREエンジニアは今後も成長し続ける。だからこそ、今動こう
ここまで読んでくださった方は、「SREって、想像以上に面白そう」「自分にもチャンスがあるかも」と思い始めているかもしれません。SREは、まさに今の時代にマッチした“これからのエンジニア”の形。そして、そのニーズは今後もどんどん広がっていくと考えられています。
SREは“なくならない仕事”。だから将来性がある
どんなに技術が進化しても、システムが止まるとサービスは止まります。
その信頼性を支えるSREの存在は、今後ますます価値が高まる仕事です。
AIや自動化が進んでも、信頼性の設計や判断は、まだまだ人間の経験と知識が不可欠。
つまり、SREはこの先も求められ続ける、安定した技術職として、大きな魅力があります。
未経験でも、今日から一歩踏み出せる
インフラ、クラウド、プログラミング、運用改善。
聞き慣れない言葉が多いかもしれませんが、最初から全部できなくて当然です。
大切なのは、興味を持ったこのタイミングで、小さな一歩を踏み出せるかどうか。
オンライン講座を1本見るでもOK。Linuxに触れてみるでもOK。
今や学習環境は揃っているので、やる気次第でいつからでもスタートできます。
未来の自分の選択肢を、今の自分が増やしてあげよう
SREという仕事には、深い技術・高い市場価値・多彩なキャリアパスという三拍子が揃っています。
“好き”と“得意”が重なる場所で、安心して長く働けるのも、この職種の強みです。
未来の自分が、「あのとき動いてよかった」と思えるように。
今この瞬間から、小さな一歩を踏み出してみませんか?
この記事が、あなたのキャリアを考えるきっかけになれば嬉しいです。
不安があっても大丈夫。まずは「興味がある」という気持ちを、大切にしてあげてくださいね。
管理人おすすめのキャリアエージェント:フォースタートアップス
もし「将来、スタートアップでSREとして活躍したい」「もっと裁量のある環境でチャレンジしたい」と感じているなら、フォースタートアップスの活用をぜひ検討してみてください。
スタートアップ業界に特化した専門エージェントで、年収1,000万円超のハイクラス案件や、CxO・経営幹部クラスの転職支援実績も豊富。非公開求人も多数あり、あなたの経験と志向に合わせたマッチングが可能です。
成長企業と向き合ってきたプロだからこそ、次のステージへと背中を押してくれます。