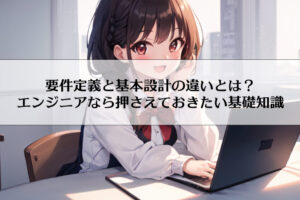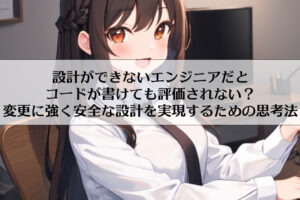こんにちは!ITキャリアのプロです!

クラス設計に悩んでいるエンジニアの方はとても多いです。設計はプログラミングの中でも特に正解が見えづらく、学べば学ぶほど迷いが深くなってしまうこともあります。この記事では、クラス設計に「難しさ」を感じる理由から、無理なく乗り越えるための考え方まで、優しく丁寧に解説していきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。
Contents
クラス設計が難しいと感じる理由とは?
設計に「正解」がないから
クラス設計には絶対的な正解がありません。ソフトウェアの仕様やチーム、プロジェクトの目的によって、最適な設計が常に変わるからです。どんなに経験豊富なエンジニアでも、状況によって答えを探りながら設計していきます。設計に悩むのは、成長している証でもあります。
ゴールがぼんやりしているから
設計をする際、最終的にどのような機能や拡張性を目指すのかが曖昧なままだと、クラス構成も迷子になりがちです。目的地がはっきりしていないと、どんな地図を作ればいいかもわからないからです。クラス設計を考えるときは、「このクラスはどんな役割を果たすのか?」を明確にすることが大切です。
若手エンジニアは「作りすぎ」や「複雑化」に陥りやすいから
経験が浅い若手エンジニアほど、教科書通りの「きれいな設計」を意識しすぎて、必要以上にクラスを分けすぎたり、抽象化しすぎてしまう傾向があります。結果、シンプルに作れるはずの機能が複雑になり、開発スピードも落ちてしまいます。まずは「動くものを早く作る」ことを優先し、設計は後から見直していく柔軟さを持つことが、現実的で効果的なアプローチになります。
クラス設計が難しいときに陥りやすい失敗例
クラス設計を始めたばかりの頃は、誰しも一度はつまずきます。特に若手エンジニアの方にとっては、「これでいいのかな?」という不安がつきまといやすいものです。ここでは、クラス設計に悩んだときに陥りがちな代表的な失敗例を取り上げ、その背景と対策をわかりやすく解説します。自分自身の成長のヒントにしてみてくださいね。
クラス設計が難しいときに陥りやすい失敗例
最初から完璧な設計を目指してしまう
最初から完璧なクラス設計を目指すのはおすすめできません。開発を進めていく中で必ず要件や状況が変化するからです。最初にどれだけ時間をかけて設計しても、実装フェーズで仕様変更が発生すれば、すべて作り直しになるリスクがあります。まずは「今わかっている範囲」でシンプルに作り、改善を重ねていく方が、結果的に効率的な設計に育ちます。
設計に時間をかけすぎて開発が進まない
クラス設計に悩みすぎると、肝心のプロダクト開発が遅れてしまう危険性があります。設計に完璧を求めるあまり、手が止まってしまうからです。特にスピード感が求められる現場では、「作りながら考える」くらいの感覚で進める方が、開発サイクルを回すことができます。設計だけに固執せず、「動くもの」を早く作る意識を持ちましょう。
実装してみたら「使いにくい」クラスになってしまった
クラス設計だけに集中しすぎると、実際に使ったときに扱いにくい構造になってしまうことがあります。設計段階では「理論的に美しい」ことを優先してしまい、現場での実用性を後回しにしがちだからです。クラスは実際に使われてこそ価値があるもの。設計を考えるときは、常に「このクラスを使う人の視点」に立って、シンプルで直感的に使える形を意識しましょう。
「設計をあえてしない」という選択肢
クラス設計に正解がないなら、そもそも「設計しない」という選択肢はどうでしょうか?最初は驚くかもしれませんが、実はこのアプローチは、現場でのスピードや柔軟性を重視する上でとても理にかなっています。ここでは「設計をあえてしない」という考え方のメリットと、実際にどう取り入れていけばよいかを、わかりやすくお伝えしていきます。
「設計をあえてしない」という選択肢
早く作り、早くフィードバックを得る
設計を最小限にしてまず動くものを作ると、フィードバックを素早く得ることができます。プロダクトの方向性や課題は、実際に動かしてみないと本当には見えてこないからです。最初に軽く作り、ユーザーやチームから意見をもらいながら柔軟に軌道修正するほうが、結果的に無駄な設計や手戻りを減らすことができ、プロジェクトを成功に近づけます。
設計にコストをかけすぎない
設計にこだわりすぎると、開発初期で大きなコストがかかり、結果としてビジネスチャンスを逃してしまうリスクがあります。特にスタートアップやスピード重視のプロジェクトでは、素早くリリースして市場の反応を見ることが最優先です。まずは最低限の設計で作り始め、必要に応じて後から拡張・リファクタリングする戦略が、限られたリソースの中では非常に効果的です。
設計は「育てる」ものと考える
最初から完璧な設計を目指すのではなく、設計もプロダクトと一緒に育てていくという考え方が大切です。開発を進める中で仕様やニーズが必ず変わります。変化に柔軟に対応できる設計は、最初からガチガチに固めたものではなく、軽やかに手直しできる設計です。「作りながら磨いていく」姿勢を持つことで、設計も自然と洗練され、成長していきます。
クラス設計がうまくなるために今できること
クラス設計の難しさを乗り越えるためには、ただ本を読むだけでは足りません。実際に手を動かし、試行錯誤を重ねながら感覚を磨いていくことが大切です。ここでは、若手エンジニアの方が今すぐ実践できる、クラス設計上達のための具体的なアクションをご紹介します。焦らず一歩ずつ取り組んで、着実に成長を実感していきましょう。
小さなプログラムから「試して」「壊して」「直す」
小さなプログラムをたくさん作って、設計を試して壊して直す経験が何よりの練習になります。座学だけでは設計の感覚を身につけることは難しく、実際に手を動かすことで初めて理解が深まります。小さな範囲で設計ミスを経験しておけば、大規模開発でも柔軟に対応できるようになります。ミニアプリや簡単なツール作りに積極的にチャレンジしてみましょう。
設計本や理論に振り回されないマインドセット
設計に関する理論や書籍はとても役立ちますが、あまりに忠実に守ろうとしすぎると、かえって柔軟な設計ができなくなることもあります。現場では理論通りにいかないことが多く、状況に応じた「割り切り」が必要です。設計理論は「参考書」として受け止め、自分なりの判断基準を育てる意識を持つことが、実践的な設計力を養う近道になります。
他人の設計をたくさん読む・レビューする
他人の書いた設計やコードを読むことも、設計力を磨くための非常に効果的な方法です。自分では思いつかないアプローチやパターンを学べます。チームメンバーのコードレビューに積極的に参加したり、オープンソースプロジェクトの設計を観察したりすることで、自然と「良い設計」「悪い設計」の違いが見えてきます。目を鍛えることも、設計力向上には欠かせません。
まとめ
ここまでクラス設計の難しさに向き合う方法を一緒に見てきました。きっと、少しでも「自分だけじゃないんだ」と安心できたのではないでしょうか。最後に、この記事でお伝えした大切なポイントをやさしく振り返りながら、これから設計とどう向き合っていくべきか、改めてまとめます。焦らず、あなたのペースで歩んでいきましょう。
クラス設計が難しいのは「普通」のこと
クラス設計を難しく感じるのはとても自然なことです。設計には絶対の正解がなく、経験や状況によって正解が変わります。若手エンジニアの段階で悩むことは、むしろ成長の証です。自信をなくさず、今のつまずきすら大切な学びとして受け止めましょう。
完璧を目指さず「まず作る」姿勢を大切に
最初から完璧な設計を目指すのではなく、まず動くものを作ることを優先する。このアプローチが、結果的にクラス設計の腕を育てる最短ルートになります。設計は作ったあとにいくらでも改善できます。まずは「動かす」こと、「フィードバックをもらう」ことに意識を向けていきましょう。
少しずつ、確実に成長していけば大丈夫
クラス設計の上達は、一朝一夕にはできません。だからこそ、小さな挑戦と試行錯誤を積み重ねることが大切です。設計を失敗しても落ち込まず、そのたびに学び、また次に活かしていけばいいのです。焦らず、少しずつ、着実に進んでいきましょう。あなたの設計力は、きっと確実に育っていきます。
管理人おすすめ|ITフリーランスエンジニア向け案件紹介サービスat-engineerのご案内
クラス設計に限らず、エンジニアとしてのスキルを伸ばしていくためには、自分に合ったプロジェクトに携わることがとても大切です。そこで今回は、若手エンジニアの皆さんにもぜひ知っていただきたい、私おすすめのエージェントサービスをご紹介します。
こちらのサービスは、ITフリーランスエンジニア向けに案件を紹介しているサイトです。ご登録いただくと、専任の営業担当者があなたのスキルや希望にマッチした案件を一緒に探してくれます。地域は東京・神奈川・千葉・埼玉、そして大阪が中心。都市部でエンジニアとしてさらにキャリアを磨きたい方にぴったりのサービスです。
特におすすめできるポイントは、エンドユーザー案件や元請け案件の割合が約78%と非常に高いこと。下請けを何重にも挟まないため、働きやすい環境や高単価を期待できます。また、即日支払いにも対応可能(別途手数料あり)なので、資金繰りの心配を減らしたいフリーランスの方にも安心してご利用いただけます。
対象となるのは、20代〜40代のITフリーランスエンジニアの方。これからフリーランスに挑戦してみたい方も、すでにご経験がある方も、幅広くサポートしてもらえます。
少しでも気になる方は、ぜひサイトをチェックしてみてくださいね。