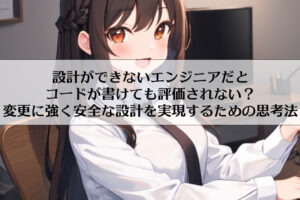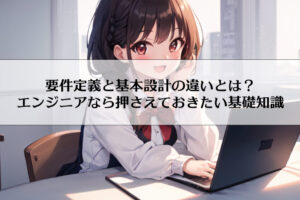こんにちは!ITキャリアのプロです。

設計を学び始めたばかりの若手エンジニアにとって、「SOLID原則」は避けて通れない定番の学習テーマです。クリーンで拡張しやすいコードを書くための原則として知られていますが、現場では「やりすぎて逆に読みにくくなった」「守ったはずなのに開発が回らない」といった声もよく聞きます。この記事では、SOLID原則を正しく理解しながらも、実務で無理なく使える“ちょうどいい設計”の考え方を、具体例とともに解説します。
Contents
「SOLIDを守っているのにしんどい」若手エンジニアが感じる違和感
原則通りなのに開発がうまく進まない理由
SOLID原則を真面目に守ろうとすると、逆に開発チームの足並みがそろわなくなったり、コードが読みにくくなったりすることがあります。理由は、クラスや責任を細かく分けすぎて、全体の流れが見えづらくなってしまうからです。
たとえば、注文処理という1つの機能をバリデーション、計算、保存、通知といった単位に分け、それぞれ別クラスにしてしまうと、全体像をつかみにくくなってしまいます。特に経験の浅いエンジニアにとっては、どのファイルがどんな役割を果たしているのかを理解するまでに時間がかかり、開発スピードが落ちてしまうこともあります。
抽象化しすぎてコードが読めなくなる
設計の原則に従って、あらゆる部分を抽象化した結果、コードの流れが追いにくくなることがあります。特にインターフェースや依存性の注入(DI)を多用すると、1つの処理の全体像を把握するために、複数のファイルや定義を追いかけなければならなくなります。
たとえば、通知処理を抽象化しすぎると、「実際には何の手段で通知されるのか(メールなのか、LINEなのか)」がすぐに分からなくなり、トレースのための時間が増えてしまいます。これは特に、小規模なプロダクトや初期段階の開発では、過剰な設計になってしまう可能性があります。
正しさを目的にしてしまっていませんか?
設計原則は、あくまでもより良い開発のための手段です。ところが、原則を守ること自体が目的化してしまうと、「本当にやりたいこと」が見えなくなってしまいます。
設計の美しさよりも、まずはユーザーに価値を届けること。機能がきちんと動いて、チームがスムーズに開発を進められること。それこそが設計の目的です。原則に縛られるのではなく、原則を“活かす”視点を大切にしたいですね。
【かんたん解説】SOLID原則とは?現場で使う意味をざっくり理解
「設計は大事」とよく言われますが、SOLID原則と聞いたときに「難しそう」「抽象的でよくわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。特に若手エンジニアにとっては、現場での活用方法や意味がいまいちピンとこないこともあるかもしれません。
この章では、SOLID原則とは何か、なぜ多くの現場で重視されているのかを、できるだけわかりやすくご紹介します。原則の言葉そのものを覚えるより、「なぜこの考え方が必要なのか」を理解することが、設計の第一歩になります。
SOLID原則は、設計の“ストレス軽減ツール”
SOLID原則とは、開発を円滑に進めるためのガイドラインです。特に大規模なプロジェクトやチーム開発において、誰がコードを書いても一定のルールが守られていることで、理解や保守が圧倒的に楽になります。
一人で開発している間は、自由な設計でも問題になることは少ないですが、複数人で開発するようになると、設計方針がバラバラなままでは後々トラブルの元になります。SOLID原則は、チーム全体に「共通の設計思考」をもたらしてくれる指針として役立ちます。
5つのルールをざっくり理解しておく
それぞれの原則は、一つ一つ見てみるとそれほど難しいものではありません。それぞれが、よくあるミスや混乱を未然に防ぐための知恵のようなものです。
- SRP(単一責任の原則):1つのクラスには1つの役割だけを持たせましょう
- OCP(開放/閉鎖の原則):既存コードを変えずに、新しい機能は追加で実装しましょう
- LSP(リスコフの置換原則):親クラスの代わりに子クラスを使っても問題が起きないようにしましょう
- ISP(インターフェース分離の原則):必要なメソッドだけに依存するようにしましょう
- DIP(依存関係逆転の原則):具体的な実装ではなく、抽象に依存するようにしましょう
これらはすべて、日々の開発でつい見落としてしまいがちなポイントをカバーしてくれる基本的な考え方です。
“意味”がわかれば、設計がラクになる
この5つのルールは、ただ覚えるだけではなく、それぞれの背景や意図を知ることがとても大切です。なぜそのルールが存在しているのかを理解できれば、場面ごとに適切に使い分けることができるようになります。
たとえば、OCPの考え方を知らずに変更を繰り返してしまうと、既存コードに余計な手を加えてしまい、思わぬバグを招くこともあります。でも「壊さずに拡張する」という意図を理解していれば、インターフェースや継承など、より安全な方法を選ぶことができるようになります。SOLID原則は、選択肢を広げてくれる「便利な道具箱」のようなものです。
やりすぎたSOLID、実はこんなに危ない!ありがちな“逆効果”5選
設計原則をしっかり守ることは素晴らしいことです。ですが、現場ではその“真面目さ”が思わぬ落とし穴になることもあります。特にSOLID原則はとても強力な考え方ですが、それを過剰に適用してしまうと、コードがかえって読みづらくなったり、開発スピードが遅くなったりすることがあるのです。
ここでは、若手エンジニアの方が特につまずきやすい「SOLIDやりすぎ」のケースを5つに分けてご紹介します。
【SRP】責任を分けすぎて、クラスが迷子になる
SRP(単一責任の原則)を厳密に意識しすぎると、どこに何が書かれているのか分からなくなってしまいます。責任ごとにクラスを分けるのは正しい考え方ですが、細かくしすぎると、逆に構造が複雑になってしまうのです。
たとえば、「注文処理」という機能を、入力チェック、価格計算、在庫確認、データ登録などに分け、それぞれを別クラスにすると、処理の全体像を把握するために多くのファイルを行き来しなければならなくなります。若手エンジニアにとっては、流れをつかむのに時間がかかり、作業効率が下がってしまいます。
【OCP】拡張にこだわりすぎて、誰も読めないコードに
OCP(開放/閉鎖の原則)では、「既存のコードは触らず、新しい機能は拡張で追加する」という姿勢が推奨されます。ですが、これを意識しすぎると、どんな小さな機能追加でも、抽象クラスやインターフェースがどんどん増えてしまい、結果としてコードの可読性が下がってしまうことがあります。
たとえば、決済方法を追加するために、PayPal用・クレジットカード用・電子マネー用と、それぞれにクラスを分けて設計したとします。拡張性は確保されますが、その分ファイル数が増え、全体の構造が見えにくくなる恐れがあります。
【LSP】継承が逆効果。子クラスがバグの原因になる
LSP(リスコフの置換原則)は、親クラスの代わりに子クラスを使っても問題が起きないように設計する考え方です。ですが、現実には子クラスが親の動作をそのまま引き継げない場合もあり、そのギャップがバグの原因になることがあります。
たとえば、「鳥」というクラスに“飛ぶ”というメソッドがあり、そこから「ペンギン」というクラスを継承したとします。ペンギンは飛べませんので、“飛ぶ”動作をそのまま継承すると、想定外の挙動が発生するかもしれません。このように、継承の設計ミスは思わぬ不具合を招くリスクがあります。
【ISP】インターフェースが細かすぎて混乱する
ISP(インターフェース分離の原則)は、必要な機能だけに依存するという方針ですが、それを意識しすぎると、インターフェースが細かく分かれすぎてしまい、逆にどれを使えば良いのか分からなくなることがあります。
たとえば、「保存」「読み込み」「削除」をそれぞれ別々のインターフェースで分けた場合、実装側で複数のインターフェースを組み合わせなければならず、複雑になりがちです。特に経験が浅い方にとっては、学習コストや実装の負荷が大きくなる原因になります。
【DIP】抽象に依存しすぎて、処理の流れが見えない
DIP(依存関係逆転の原則)は、具体的なクラスに依存せず、抽象(インターフェースなど)に依存するという考え方です。しかし、それを徹底しすぎると、コードの流れを追うのが難しくなってしまうこともあります。
たとえば、通知機能を「INotifier」インターフェースで抽象化し、その中身として「SMS通知」や「メール通知」をDIで注入する設計にしたとします。この場合、処理の全体像を把握するために、DI設定やインターフェースの定義、実装クラスをすべて確認しなければなりません。特に小規模なプロジェクトでは、そこまでの抽象化が必要でないケースも多いです。
PDFに学ぶ「正しいSOLID」と、やりすぎを防ぐコツ
設計原則は、学ぶときに誤解されやすいものです。特にSOLID原則は「必ず守らなければならない厳格なルール」として受け止めてしまうと、現場で窮屈な設計になってしまうこともあります。
本来のSOLID原則は、開発をより快適に、安定的に進めるための“道しるべ”です。この章では、バランスよく使いこなすための考え方と、実務で活かすための視点についてご紹介します。
原則を“絵に描いた餅”にしない
設計原則は、教科書や資料でよく図解されていますが、「図や言葉だけで理解した気になる」のは危険です。大切なのは、その原則が現場でどう機能するのか、どう役立つのかを自分なりにイメージできることです。
たとえば、「1つの責任に分ける」と書かれていても、それがどこまで細かく、どのように分けるべきかはプロダクトによって異なります。責任をどう切り分けるかは状況次第です。実際のプロダクトに当てはめながら考えることで、原則の“正しい意味”が自然と身についていきます。
“変化しやすいところ”を見極める設計目線
SOLID原則の多くは、「将来的な変更に強くなること」を目的としています。ですが、すべてのコードを過剰に抽象化する必要はありません。むしろ、大切なのは“よく変わる部分”を見極めて、そこにだけしっかり原則を活かすことです。
たとえば、今後さまざまな決済方法が追加される予定があるなら、その部分にはOCP(開放/閉鎖の原則)を意識した設計が必要です。一方で、ほとんど変更されないような定数管理などにまで抽象化を適用してしまうと、逆に過剰設計になってしまいます。
軽やかに、設計と向き合っていく
SOLID原則を守ることに必死になるのではなく、設計と“対話するように向き合う姿勢”がとても大切です。原則を支配的なルールとして受け入れるのではなく、「今の開発に役立つか?」という目線で柔軟に活用していきましょう。
実際には、SOLID以外にもDRY(同じことを繰り返さない)やSLAP(1つの抽象レベルに絞る)といった原則もあります。いろいろな設計の考え方をうまく組み合わせながら、場面に応じて適切な設計手法を選ぶことが、設計力を高める一番の近道です。
【まとめ】”SOLID原則”の本当の価値は「コードの快適さ」にある
ここまで、SOLID原則の基本、やりすぎた場合の副作用、そしてちょうどよく使いこなすためのコツについてご紹介してきました。原則を100%完璧に守ることがゴールではありません。本当に大切なのは、「自分たちのチームにとって、気持ちよく使える設計になっているかどうか」です。
“美しい設計”よりも“心地よい設計”を
設計が芸術作品のように美しく整っていても、誰にも理解されず、変更もしにくいのであれば意味がありません。実務では、リリーススピードや保守性、チームでの連携のしやすさが最も重要です。
多少原則から外れていても、読みやすく、安心して触れるコードであれば、それは“良い設計”だと胸を張って言って大丈夫です。
チームによって“ちょうどよさ”は違う
SOLID原則の「ちょうどいい使い方」は、チームの人数、スキル、プロダクトの段階によって異なります。スタートアップのようなスピード重視の現場と、安定運用を求められる企業開発では、設計のアプローチも変わってくるのは当然です。
その時その場に合った“快適な設計”を目指すことが、設計スキルを磨く第一歩になります。
原則は“引き算”で使うと一人前
設計力がある人は、たくさんのルールを覚えている人ではありません。「これは必要ない」「ここはあえて簡単にしておこう」と、うまく“引き算”ができる人です。
設計は足し算ではなく、むしろ引き算の連続です。今のチームにとって、今のプロダクトにとって、本当に必要な設計だけを選んでいく。その判断ができるようになると、自然とSOLID原則も“自分のもの”として使いこなせるようになります。
管理人おすすめのエージェント:スタートアップで本気の挑戦をしたいあなたへ
設計に向き合い、SOLID原則のような深い技術テーマに取り組むエンジニアの皆さんには、キャリアについても“自分らしく設計”してほしいと考えています。もし、今の働き方に少しでもモヤモヤを感じていたり、「もっと成長できる環境に挑戦したい」と思っているなら、スタートアップ転職に強いエージェントを味方につけるのも一つの選択肢です。
私がおすすめしたいのは、フォースタートアップスというエージェントサービスです。
スタートアップに特化したキャリア支援を行っており、これまで1,200名以上のCxO・幹部クラスの転職を支援してきた実績があります。支援対象はハイクラスだけでなく、将来的にプロダクトリードや技術責任者を目指したい若手エンジニアの方にも非常にマッチしています。
フォースタートアップスのここがすごい
- スタートアップ特化の専門コンサルタントがマンツーマンでサポート
- 年収1,000万円以上の非公開求人も多数
- 「本気でプロダクトに向き合える環境」に出会える
- 技術だけでなく、キャリア設計や働き方についても相談できる
私自身、キャリアの悩みを誰にも相談できなかった時期があったからこそ、「信頼できる人と話せること」の大切さを強く感じています。もし今、新しいステージに進みたいと考えているなら、まずは一度気軽に相談してみてはいかがでしょうか?